 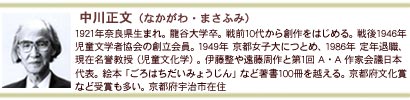 |
|
− 23 − 『もりのなか』への回り道 |
東京へ行くたびに松居家に居候並みに泊りこみ、そのたびに増殖する海外からとどく絵本に驚いたものです。 わたしにしても十代から幸運にも児童文学の同人誌に参加することを許され、雑誌の同人たち(勿論ずっと年嵩の先輩)などと文学や童謡について批判しあったり討論したりしていたので、おぼろ気ながら絵本というものの存在を気にしてはいました。 それなりに絵本の理想像を描いては、あるときに机をたたいて激しく論じあったものでしたが、今にして思えば、世界の絵本の状況については全く無知のくせに机上で空論のやりとりをしていたものです。 松居家は、次々にとどく世界の絵本をさりげなく私に示しては、声もたてられないくらいの「目からウロコ」状の私を慌てさせてくれました。 そういう時代が何と数十年ちかく続いたような実感が残っていますが、実際は数年に過ぎなかったかもしれません。その絵本たちに関しては後で一冊ずつ対応を書くつもりですが、そういう新鮮な絵本への衝撃も衝撃でしたが、更に私を驚かせたのは、松居さんは絵本をタブロウのような単なる美術作品ではなく、またいわゆる文学でもない子どもとわたしたちをつなぐ、子どもにとっての初めての文化——こういう聖書の箴言のような姿勢でした。 そのころわたしは、戦時中に書いた童話を含め、敗戦直後の半年間の生家のある大和村の生活を描いた童話集をすでに出版していましたし、各地の童話作家との文学的な交流を拡げていて、自覚的には児童文学者としての自負を抱えていたのです。作家はいかなる作品を、いかに巧妙に感動的に描くか——これが最も主体的な重要な認識であるべき、と思いこんでいたのです。誠に現在では信じられない幼稚な地点で、なり振りかまわず厖大な習作を書き散らしていたのです。 そういう子ども忘れの無謀なわたしを前にして、松居さんは素知らぬ振りをして、シャカを題材にした長編童話を書くように奨め、旧東海道線の汽車で京都へ往還を繰りかえしては、インドの仏教美術の専門家にひきあわせたり、そのころ松居さんが深くかかわろうとしていた石井桃子さんや、瀬田貞二、渡辺茂男さんなど、当時としては日本の児童文学の最先端の真当な人びとに個人的にも直接近づけたりしてもらった——にもかかわらず私などなかなか松居さんの真意が理解できないで、文学者として芸術に携わるものは、対称として子どもなど考慮に入れないことが作家としての純粋さ、芸術としての高さなどと固執していたものです。 それも松居さんに出会うまえ、年端もゆかぬ十代の中頃から同人誌の先輩として、また同人誌の伴走者としての花岡大学の文学論が、私を閉じ込めていたような気がします。 一まわり年上の花岡大学は、いつも逢えば熱狂的に私に吹きこんでいました。 オレの児童文学は程度の低い子どもたちを相手にしない。百人の子どもがおれば一人くらいは優れた子どもがいる筈だ。オレはそいつらのために書く。あとの九十九人クラスの奴らが、オレの童話を読んだために下痢をしたり傷ついたりしてもオレには責任ない。作家の関知するところではない。だから芸術といえるのだ…。 彼は繰り返し繰り返し主張したものの、世間の主な児童文学者たちがとりあわないので、攻撃の目標をわたしに絞った気配でした。 そのせいか松居さんからもらったシャカものの長編童話も、わたし自身ひとりが興味あるブッダ観としての、主題「目の見えるものに見えなくて、目が見えないものだけに見える世界」にこだわって、なかなかプロットの導入すら展開できず、編集長松居直さんを困らせてしまうことになりました。 そういう状況は解消しそうになかったのですが、具体的な絵本のちからは思いがけず強力だったのです。やはり、わたしを子どもの世界に押しもどしてくれたのです。 その絵本こそ、松居家で見せてもらった多くの絵本のなかで、墨一色でやさしく息づいていた、マリー・ホール・エッツの『もりのなか』だったのです。 |
「絵本フォーラム」57号・2008.03.10
前へ★次へ
