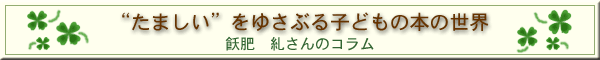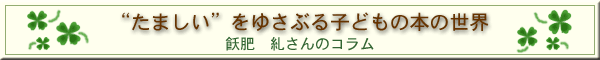「絵本フォーラム」第33号・2004.03.10
●●22
広がる大草原が生むのか。少年のしたたかな優しさ
『スーホの白い馬』
 国技とされる大相撲の世界にモンゴル旋風が起きている。唯一の横綱は朝青龍だし、旭鷲山など有力力士が幕内上位に顔を並べる。そんなこともあるだろう。モンゴルの国情や人々の暮らしぶりが紹介されることが多くなった。モンゴルの人々は11〜12世紀に北東アジアに現れた少数民族で、多くが遊牧民であったことで知られる。遊牧民は移動しながら大草原で羊や牛、馬、駱駝を放牧し、毛氈で作ったテントで生活する。日本人に名高いのはモンゴル政権を樹立したチンギス・ハンや、13世紀後半に中国・元王朝を創ったチンギスの孫・フビライ・ハンの英雄伝であろうか。
国技とされる大相撲の世界にモンゴル旋風が起きている。唯一の横綱は朝青龍だし、旭鷲山など有力力士が幕内上位に顔を並べる。そんなこともあるだろう。モンゴルの国情や人々の暮らしぶりが紹介されることが多くなった。モンゴルの人々は11〜12世紀に北東アジアに現れた少数民族で、多くが遊牧民であったことで知られる。遊牧民は移動しながら大草原で羊や牛、馬、駱駝を放牧し、毛氈で作ったテントで生活する。日本人に名高いのはモンゴル政権を樹立したチンギス・ハンや、13世紀後半に中国・元王朝を創ったチンギスの孫・フビライ・ハンの英雄伝であろうか。
現在のモンゴル人民共和国は、156万平方キロと広大な国土に僅か200万人弱の国民。広くて小さな国だ。海に囲まれた狭い国土に1億2000万人強が住む日本と対照的である。モンゴルを訪れたことがなくイメージできないが、物事に動じない個性に対し形容される“大陸的”という言葉を実感できる大地や大草原に一度は触れてみたいと思う。果たして中央アジアや北東アジアの大地に両の足を落ち着かせれば“大陸的”な気分を感じ取ることができるだろうか。
赤羽末吉の描くモンゴルはすごい(大塚勇三・再話『スーホの白い馬』)。大草原という言葉を視覚に置き換えて圧倒するほどに眼前に展開する。実際はどうであるか検証できないが、12、13世紀のモンゴルはこうであったろう、と充分にイメージさせてくれる。ぐいぐいっと、ぼくを引き寄せる図絵である。
彼は、横32縦24センチの大きな横長頁を大胆な見開き断ち落としで23場面、丁寧に物語の運びに配意しながら描き込む。大地は雄大で広大であり、点在する人々の存在が別世界のように不思議に映る。自然のままに放り出された大地と人間の関わりはどのようなものか、思案させられるのである。赤羽の絵作りだけを語るのが本稿の目的ではないが、果てしない地平線や草原に覆いかぶさる巨きな虹、広大な舞台で展開される競馬の場面。さらには悩みぬいたに違いない色彩や色調などに、彼の情熱やエネルギーがどれほど費やされたかと、壮大な大陸図絵に囚われてしまうのである。
『スーホの白い馬』はモンゴルに古くから語り継がれてきた民話である。
おばあさんとふたりで草原に住む貧しい羊飼いの少年・スーホと、彼が見つけた白い仔馬が主人公。大人にも負けない働き者で歌上手のスーホは、草原にはるかに響きわたる美しい声でよく唄い羊飼いの仲間たちを喜ばせる少年だった。スーホは白い仔馬を精一杯の愛情を込めて育てる。スーホはこの馬で殿様の主催する競馬大会に出場し見事に優勝。ところが、殿はご乱心、すっかりこの馬を気に入り取り上げてしまう。馬はスーホのもとへ戻ろうと、試乗する殿を振り落とす。怒った殿は家来に矢を放たせるが馬は傷つきながらもスーホのもとに戻り命を落とす。古今東西何処も同じで、権力者・殿様には金や武力で獲得できないものがあることなど理解できないらしい。果てしない大草原が育んだのか、スーホと白い馬の情愛は金や武力よりもはるかに強かったのである。
スーホや白い馬の優しい心情を大塚勇三が抑制の効いた淡々とした言葉で綴り、胸を打つ感動的な良質な物語にしている。話はここで留まらず民族楽器として知られる馬頭琴の由来が、愛馬の亡骸で楽器を造る夢をスーホが見たことにあると物語る。やがて馬頭琴は、その美しい音色でモンゴルの羊飼いたちの心を癒す楽器に、というお話しで幕。愛する者の亡骸をぼくらは加工して手許に置けるだろうか。
何世代も語り継がれる民話は、少しずつ時代の装いで変容するだろうが何人にも通じる理と民族独自の特異な個性を内に包んで次世代へと語り送られる。 |