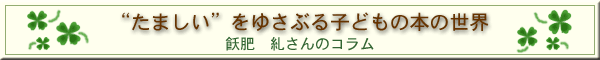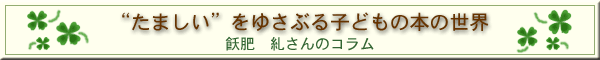「絵本フォーラム」第19号・2001.11
●●8
みんなみんな、食いしんぼ
 飽食の時代といわれる。全くその通りだと思う。東京や大阪、博多など繁華街・飲食店街などから連日連夜吐き出される残飯の量はものすごい。家庭の食卓も同じように飽食の光景が日常となっているのではないか。人が人として生きることのできる必要摂取量の数百万人分の食糧を連日捨てている勘定になるのだという。
飽食の時代といわれる。全くその通りだと思う。東京や大阪、博多など繁華街・飲食店街などから連日連夜吐き出される残飯の量はものすごい。家庭の食卓も同じように飽食の光景が日常となっているのではないか。人が人として生きることのできる必要摂取量の数百万人分の食糧を連日捨てている勘定になるのだという。
一方で、住む家もなくボロを纏い、雨溜まりに口を寄せ泥水を飲むしかない夥しい数の難民たちがいる。難民発生地域で食に飢えて亡くなってゆく人々にぼくらはどれほど思いを馳せているだろうか。
情けないことだが小生も大食漢の食いしんぼ。せめて好き嫌いなく、残飯など残さぬようにひと粒の米たりとたいらげることで無駄だけは止そうとこころがけて、こころの痛みをやわらげるのがせいいっぱいのだらしなさである。
「衣・食・住」をくらしの3原則といい、「衣食足りて礼節を知る」という。だが、何と言おうとまずは食だろう。生命体の細胞分子を機能させ活力エネルギー源となる食なくして人はひととして成り立たない。食のありがたさ、食を獲得することの大切さをぼくらはすっかり忘れてしまってはいないだろうか。
ぼくは終戦に至る7ヶ月前に中国大連に生まれ、戦後1947年に父の郷里に引き揚げた。両親ともに教師であったが子どもは6人。8人家族の大家族であった。大家族といっても8人や10人といった家庭が一般的であったから当時としてはごく普通の家族構成であった。
戦後間近から15年ほどのあいだ、日本の庶民の食卓は、現在とはとても比較などできないくらい貧しかった。しかし、比喩的に表現すれば、とてもとても現在と比較なんかできるものかと突き放したくなるほどにゆたかさに満ちていた。 何処の家庭でも庭先にちいさな畑を持ち白菜や大根などの食材を栽培し、鶏がのんびり遊んでいた。それらの食材に魚貝など、わずかばかりの購入食材を加えて母は料理の腕をふるった。魚を三枚におろし、自家製醤油や野菜汁で味付けしてゆく我が家の料理は少ない食材から多彩なメニューを生み出していた。外食など生活習慣の外にあり、いつも家族総員が食卓を囲むのがあたりまえであった。おやつを貰えるのはたまのこと。貰える場合もおやつはもっぱら薩摩芋だった。蒸かしイモ、焼きイモ、干しイモ、米と合わせたイモだんごなど、手品のように母はつくった。だから、そんな廉価なおやつでも待ち遠しく貴い愉しみだった。ぼくら子どもにとって食する楽しみは何にもまして喜びであった。食は尊い貴いものだった。
ぼくらのなまえは ぐりとぐら
このよでいちばん すきなのは
おりょうりすること たべること
ぐり ぐら ぐり ぐら
こんな、唄を口ずさめるようなリズミカルな調子のことばで物語りが運ばれてゆくとてもユーモアたっぷりの絵本がある。(『ぐりとぐら』中川李枝子/大村百合子作、福音館書店)
主人公はのねずみのぐりとぐら。森にでかけたふたりは大きな大きな卵を見つけ、この卵でカステラづくりに挑戦。なべやら材料やら持ってきて森の中での料理のはじまり。甘くておいそしうな匂いが森中に広がって動物たちが集まってくる。そして、黄金色のカステラができあがると…。みんなにカステラをわけてやる可愛いぐりとぐら。カステラのできるようすをワクワクしながら見つめる動物たち。
白地にシンプルでやわらかい描線を走らせ最小限の彩色で描きあげられたこの絵本は、無条件に、子どもたちやぼくら大人たちにまであたたかいぬくもりを伝え与えてくれる。そして、食することの大切さや、みんなで分け合って食するよろこびを絵画やリズム感いっぱいのことばにいつのまにか忍ばせているのである。
作者の中川李枝子もまた、幼年時、決して豊かでない食状況のなかで育ち、食の大事さ、有難さ、よろこびを身を持って知った、と語っている。そののち長い保育士としての体験から『ぐりとぐら』のほか数々の名作を生み出している。 |