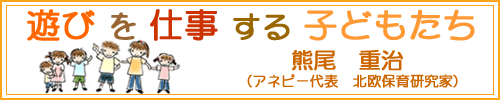 − 5 − 絵本と遊具 今年初め、ほるぷフォーラムが5月より「絵本講師養成講座」をスタートするという、大変喜ばしいお話を伺いました。この有意義な講座の誕生に刺激され、今回は「絵本と遊具」と題し、絵本と比較することによって、子どもにとって遊具とはどのようなものか、よい遊具とはどのような機能を持ったものかを考えてみることにしました。 残念ながら、絵本と違って遊具の世界には、作家もいなければ、それを専門として研究している人もいません。したがって、考えとしては不十分なものにならざるを得ませんが、よい遊具選定の参考になると同時に、絵本についても、その価値を再認識していただけるのではないかと期待しています。 最初に、遊具とは何か、乳幼児が成長していく過程で遊具はどのような役割を果たしているかを理解しやすくするため、絵本と遊具の違いに注目し、比較表を作成しました(表「絵本と遊具の違いに重点を置いた比較表」)。
「子どもにとって遊ぶことは重要」「絵本と遊具は子どもの成長において必要不可欠」とよく言われますが、そのことがこの比較表により証明されると思います。 次に、「よい絵本とはどのようなものか」ということから、よい遊具の条件について考えてみました。現時点での私の結論は、以下のようになります。 よい絵本とは、子どもに新しい知識を与え、好奇心と夢を抱かせ、未来に希望を持たせるものだと思います。したがって、子どもの年齢や成長に応じて、新しいもの、未知のもの、あるいは普通の日常生活にはない出来事や、ファンタジーの世界が描かれたものを選び、与えることが重要だと思われます。 同じように、よい遊具とは、身体に新しい体力を与え、勇気と冒険心を抱かせ、生きていく自信を持たせるものです。したがって、すべての身体機能を使わせる構造となっている部材を多く備えた遊具こそが優れたものだと言えるのです。 具体的には、日常生活ではあまり使わない身体機能、すなわち、「飛ぶ」「揺れる」「腕を使って登り降りする」「渡る」などの機能が備わっているもの、あるいは、それらの動作を複合的に必要とする遊具です。 もう一つ重要なことは、1枚の絵がどんなに優れていても、そこに物語性がなければ「絵本」にはなりません。遊具も同じで、例えばつり橋やロープウェーなど、機能が複合していると同時に、物語性、すなわち、連続性、回遊性を多く満たしていることが必要な要素となってきます。 乳幼児を対象に新幹線や船、飛行機、恐竜など、単体の遊具が多く設置されていますが、これらはデザインや形はよくても、遊びの機能が乏しいため、よい遊具とは言えません。本当は、運動能力が十分発達していない乳幼児にこそ、複合遊具が必要なのです。 公園、幼稚園、保育園の園庭に、複合的な機能を持ち、遊びの要素をたくさん含んだ遊具が設置されているかどうか、注意してごらんいただければ幸いです。 |
前へ★次へ
