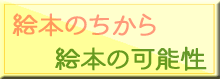
|
★特別編★ 「絵本フォーラム」31号・2003.11.10 |
 柳田 邦男(やなぎだ くにお)氏 略歴 1936年栃木県生まれ。NHK記者を経て、ノンフィクション作家に。1972年『マッハの恐怖』で、第3回大宅壮「ノンフィクション賞」を受賞。1995年『犠牲(サクリファイス)わが息子・脳死の11日』とノンフィクション・ジャンルの確立への貢献で第43回菊池寛賞を受賞。 『ガン回廊の朝』『空白の天気図』『「死の医学」への日記』『読むことは生きること』など著書多数。 | |
|
柳田 邦男(ノンフィクション作家) | |
|
小児科医の細谷亮太先生から、一冊の新しい絵本が送られてきた。明かるい太陽と天高く伸びた木々の若葉を背景に、小学校低学年くらいのおにいちゃんと妹の並んだ姿の絵が、表紙のカバーに描かれている。とてもあたたかい色調の絵柄だ。題は『おにいちゃんがいてよかった』(岩崎書店)とある。 《あ、できたんだ。》 細谷先生が新しい絵本づくりに取り組んでいると聞いたのは、一昨年だった。どんな絵本を構想しているのか、たのしみにしていた。 細谷先生は、長年にわたって東京・中央区にある聖路加国際病院で、小児がんなどの子どもたちの治療とケアに携ってきた。『川の見える病院から』(最近講談社+α(プラスアルファ)文庫に『医師としてできることできなかったこと』と改題して収められた)など、病気の子どもや親たちのエピソードを軸にした、胸がじーんと熱くなるエッセイ集を書いているし、最近は大きな感動を呼んだNHKスペシャル『こども・輝けいのち 第4集小さな勇士たち〜小児病棟ふれあい日記〜』にも出演しているので、ご存知の方も多いだろう。 私が細谷先生と親しくなったのは、20年ほど前のこと。白血病の子どもと親を支えるアメリカのハンドブックや絵本を日本に紹介する仕事で知り合ったのがきっかけだった。薬の副作用で髪の毛が抜けてしまう白血病の子どもをクラスメートたちに理解させることをテーマにしたシュルツの絵本『チャーリー・ブラウンなぜなんだい』(岩崎書店)を翻訳して日本に広めたのも、細谷先生だ。 小児がんの子どもたちを、ただ医学的に治療するだけでなく、病気の子どもや親たちの心を支えるためのさまざまな活動に努めてきた細谷先生は、数年前に自ら絵本づくりに取り組んだ。『ぼくのいのち』(岩崎書店)がそれだった。絵は細谷先生のエッセイ集のさしえを担当した永井泰子さんが描いた。 幼い頃に白血病を克服したぼくが主人公。ぼくは夏休みにおばあちゃんちのおくらをたんけんして、一冊のアルバムを見つける。お母さんにだっこされてる頭のつるつるした小さな子がいる。そのアルバムをお母さんに見せて、その子のことを尋ねると、ぼくが小さい頃に病気をしたときの写真だと言う。その病気のことを知りたくなったぼくは、お母さんにすすめられて、病院の先生を訪ねる。 すると、ぼくは白血病だったけれど、薬で治ったこと、同じ病室にいて、一緒に雪を見た男の子も元気になって、今サッカーに夢中になっていること、ぼくと一緒に先生と芝生に寝ころんで話をした女の子は治らないで、家で家族にあたたかくかこまれて亡くなったことなど、病院で仲良くしたいろいろな友だちのその後のことを知る。 元気でいる子も、もういない子も、みんな心の中で生きているだいじな友だちだ。懐かしさでいっぱい。帰り道、緑の木立ちの横を走るぼくの頭の中に、言葉が浮かぶ。 〈いつもとおなじ木立のみどり/いつもとおなじ日のひかり。/だけどきょうはいつもとちがう。/とてもきれい。〉 このさりげないラストシーンが、私は好きだ。少年なりに「生と死」を身近に知り、生きている自分のいのちの重みを感じたとき、風景がいつもと違って美しく見えてくる。病気を克服して生きていることのすばらしさと同時に、亡くなった子を偲んでいとおしむ心の大切さを、このような形で語りかけるのは、数々の喜びと悲しみを見つめてきた小児科医ならではの視点だろう。  その細谷先生が次に書いたのが、『おにいちゃんがいてよかった』なのだ。絵は今度も永井泰子さん。
その細谷先生が次に書いたのが、『おにいちゃんがいてよかった』なのだ。絵は今度も永井泰子さん。おにいちゃんを病気で亡くした女の子「みなみ」が主人公だ。お母さんと公園に行っても、ケーキを食べるときも、おにいちゃんがいた頃の思い出で胸がしめつけられる。両親が病院に行って、ひとりで留守番したときのさびしさ。急に病院に連れていかれたけれど、おにいちゃんはすでに…。 でも、お母さんがみなみをしっかりと抱きしめてくれた。「みなみは、がんばって、よくおるすばんしてくれたね。ほんとうにありがとう」「さびしかったわよね。あのときは、みなみのはなしもゆっくりきいてあげられなかった…。ごめんね、みなみ」 これ、すごくだいじなことを語っている。私の知り合いの主婦Tさんの体験を連想するのだ。しばらく前のことになるが、Tさんは小学生だった長女が白血病になった。長女は3年におよぶ闘病の末に亡くなった。その間、Tさんは長女のケアに懸命になっていたあまり、もう一人の子であるおにいちゃんのめんどうをみるのを忘れていた。おにいちゃんは孤独でさびしかったのだ。 長女が亡くなった後、おにいちゃんの反抗が始まった。非行に走るようになった。Tさんも夫も、はじめは叱るだけだったが、Tさんは長男の反逆の理由に気づいたとき、涙を流して長男にあやまった。「ごめんなさい、ごめんなさい、あの子のことばかりに気持ちを奪われて」と。それから長男は落ち着いた生活に戻り始めたという。 このような落とし穴にはまる家族が何と多いことか。子どもは親からしっかりと均等に愛されたいという無意識の願望を抱いている。しかし、複数の兄弟姉妹の誰かに病気などの問題が生じると、親はその子のケアに心を奪われ、他の子どもたちを犠牲にしがちだ。 『おにいちゃんがいてよかった』のお母さんは、みなみちゃんをしっかりと抱きしめて、「ほんとうにありがとう」と言って、みなみちゃんが頑張ってくれたことを認め、さびしい思いをさせたことについても、「ごめんね」とあやまっている。そして最後には、ケーキをおにいちゃんの分も含めて四つに切って、家族四人みなそれぞれに同じようにだいじな存在なのだという意識を表現している。 「小児科医は患児だけでなく、親や家に残されたきょうだいのことまで視野に入れて、そのケアにあたる必要があるのです」と、細谷先生は語る。 細谷先生が若い駆け出しの医師だった頃、自分が担当した患児の死をはじめて体験したときに詠んだ俳句がある。 凭(よ)られても患児の軽し初時雨 みとることなりはひとして冬の紅 こういう悲しみと辛さを背負う小児病棟に勤務して30年、やさしさに満ちた感性が、医学だけでは対応し切れない課題に向き合うなかで、重い病気の子をかかえる家族に語りかける方法として、絵本を生み出したのだろう。絵本には、こんなすばらしい可能性もあるのだ。 | |
前へ★次へ
