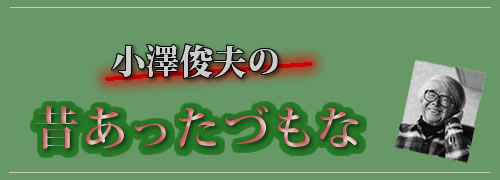「文官統制は軍部暴走の反省ではない」と中谷防衛大臣
政府は、文官統制廃止などを盛り込んだ防衛省設置法改正案を三月上旬に閣議決定する方針とのことだが、防衛省の文官統制を廃止すると、民主主義の根幹をなす文民統制(シビリアンコントロール)が骨抜きになるという強い批判がある。
ところが、二月二十七日東京新聞朝刊によれば、中谷防衛大臣は、記者会見で、「文官統制の規定は軍部が暴走した戦前の反省から作られたのか」と質問されると、「その辺は、私、その後生まれたわけで、当時、どういう趣旨かどうかは分からない」と答えたということだ。そして、記者が「戦前の軍部が独走した反省から、先人の政治家たちが作ったと考えるか」と質問すると、「そういうふうに私は思わない」と答えたという。
だが、高校生だったぼくははっきり覚えている。敗戦後、新憲法が制定され、それに基づいていろいろな法律が作られ、自衛隊が創設されたとき、戦前に軍部が独走して、満州事変、支那事変へとこの国を引きずり込んでいった反省から、「文民統制」が必須であるとの意見が圧倒的に強く、誰も疑わずに、自衛隊での「文官統制」が規定されたのである。あの重要な議論の記録が防衛省に残っていないはずはない。それは、「私、その後生まれたわけで、当時、どういう趣旨かどうかはわからない」で済まされることではない。もし、「生まれる前だから知らない」で済まされるのだとしたら、「現行憲法」についても、それで済まされるのではないか。「私、うまれる前ですから、わかりません」。そんなことはあり得ない。
しかも、一大臣が「生まれてないからわかりません」と言って、一大臣の判断で、民主主義の根幹をなす概念と制度を抹殺していいのか。
歴史の反省に立った法律でも、こんな論理とやり方で変えることができると安倍内閣は考えているのだろう。これは極めて重大な問題である。野党もマスコミも、正面から取り上げて追及しなければならないはずである。だが、ほとんど追及していない。われわれ庶民のほうからマスコミの尻を叩かなければならない。
マスコミ業界の記者たちが、こういうことの重大さに気が付かなくなっているのだろうか。しかし、耳と頭を研ぎすませて、政治家の傲慢と怠慢と無知に鞭を当ててもらいたい。この国が歴史の岐路に立っている今、マスコミ業界の記者たちの奮起を求めたい。(2015.3.4)
天皇・皇后ご夫妻の精いっぱいの意思表示
天皇・皇后ご夫妻がパラオ群島に慰霊の旅をなされた。あの大戦中に少年時代を過ごされた天皇陛下が長年にわたって実行してこられた、慰霊の旅の一環である。
新聞報道によれば、天皇陛下は出発に先立ち、皇太子、秋篠宮、安倍首相らを前に、「太平洋に浮かぶ美しい島々で、このような悲しい歴史があったことを、私どもは決して忘れてはならないと思います」と述べられたということだ。
この言葉は明らかに「そして、この多くの犠牲者のおかげで私たちが獲得した日本国憲法をきちっと守っていくことが大切なのです」と続くはずの言葉である。しかし、天皇・皇后ご夫妻としては、日本国の象徴なのだから、そこまでは言えないと思って、遠慮なさったのであろう。
ぼくはそこまで言ってもらいたかったと思うが、それは理解する。 しかし、そこまで言わなくても、天皇・皇后ご夫妻が平和憲法を守ろうと思っておられることは、誰でも推測できることである。そして天皇陛下のこの言葉は、今、アメリカ、ドイツ、中国、韓国が日本の安倍政権に対して言っている「過去の歴史を歪曲するな」「歴史を直視せよ」という批判と同じことを言っているのである。マスメディアには、この関連を強く指摘してもらいたいと思う。そうでないと、天皇・皇后ご夫妻が精いっぱい言われたその心が、国中に広がっていかないからである。
ぼくらは、みんなで、天皇・皇后ご夫妻の志をサポートしようではないか。
天皇陛下は、戦後七十年となる今年の新年の感想で、「満州事変に始まるこの戦争の歴史を十分に学び、今後の日本のあり方を考えていくことが、今、極めて大切なことだと思っています」と記しておられた。この言葉から考えても、天皇陛下が、「過去の歴史を歪曲するな」「歴史を直視せよ」と考えておられることは明らかである。ただ、お立場としてこんな激しい表現はなさらないだけのことだ。そこを、われわれは正しく理解しなければいけない。われわれ民衆の使い慣れた言葉で言い直せば、「平和憲法を守れ」「戦争反対」なのである。
ところが安倍首相は、聞いて聞かぬふりをしている。
天皇・皇后ご夫妻から直接、上の言葉を聞いたはずなのに、安倍首相は、「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)を18年ぶりに改定して、自衛隊による集団的自衛権を使った機雷除去を盛り込む方針を固めた。これは安全保障法制の大改革の一環で、ホルムズ海峡の機雷除去ができる根拠を作ろうとしているのである。安倍首相の考える安全保障法制が整備されると、他国どうしの戦争中の機雷除去もできるようになる。そして地球の裏側にまで自衛隊を派遣できるようになる。
安倍首相は「国民の生命の安全のために」と言うが、実は日本を「戦争のできる国」にしてアメリカ軍の実戦に協力することなのである。日本の総理大臣が、日本国の象徴である天皇陛下の意思を無視して、日本国を反対の方向へ強引に引きずり込もうとしている。だが「この戦争の歴史を十分に学び、今後の日本のあり方を考えていくことが、今、極めて大切なこと」なのである。(2015.4.10)
教科書を支配しようとする安倍首相
教科書の検定作業において「尖閣諸島」や「従軍慰安婦」について、「政府見解」を取り入れた記述にするよう、文科省が各教科書会社に求めたとのことである。日本は、昭和の初めころから無謀な戦争に突っ込んでいったことへの反省として、教育を時の権力のもとにおいてはいけない、という大方針を打ち立ててこれまでやって来たのである。戦争の惨禍を真摯に振り返って生まれてきた、国家としての大方針である。
国民一人一人が、自分の頭で考えることをやめ、時の政府の号令通りに行動することが、いかに危険なことであるか、日本人はあの戦争で学んだ。その深刻な反省から教育の独立性が叫ばれ、教育委員会制度が生まれ、国定教科書が廃止されたのである。それを、安倍首相と政府は、ほとんど議論もなしに変更している。断じて認めることはできない。
大学に国旗、国歌を強要し始めた安倍首相
大学に国旗、国歌を強要し始めた安倍首相 安倍首相は大学の入学式や卒後式で、国旗掲揚、国歌斉唱がされるべきではないか、と述べたということだ。そして、下村文科相も、「各大学で適切な対応がとられるよう要請したい」と述べたという。これは全く、大学への不当な介入である。
要請の根拠として、国旗・国歌法を挙げたとのことだが、この法律の審議の際には、「国として強制や義務化をすることはない」と政府は述べていたはずだ。なのに、文科省は小中高の学習指導要領に基づいて、全国の小中高校に国旗掲揚と国歌斉唱を強制している。今度は、大学にも強制しようとし始めたのである。しかも、文科省の発表を見ると、国立大学86校で、どこが国旗、国歌を実行しているのか、すでに調査済みであったことがわかる。
恐ろしいことである。 文科省は、「大学に指導や強制はできない」としているそうだが、国立大学の学長が参加する会議で要請するつもりだという。形は「要請」だが、国立大学は法人になったとはいえ文科省からの交付金がなければ成り立たないのだから、文科省からの要請は無視できないだろう。そうなると、これはもう文科省からの強制と同じだ。こんなことを認めるわけにはいかない。
大学の自治は、民主主義国家の基本的条件である。それが冒されようとしている。昭和初期の、軍部が台頭しつつあった時代と極めて似てきた。
マスメディアにも圧力をかける安倍自民党
新聞報道によれば、自民党は昨年の衆議院選挙前、テレビ朝日の番組内容に対して、「公平中立」を求める文書を出していたとのことである。報道ステーションが、「アベノミクスの効果が大企業や富裕層にのみ及び、それ以外の国民には及んでいないかのごとく断定する内容」であると批判し、「放送法に照らし、同番組の編集及びスタジオの解説は十分な意を尽くしているとは言えない」と指摘したとのことである。
マスメディアに対して、これほどあからさまの圧力をかけるとは、安倍自民党は全く思い上がっている。しかも、自民党が指摘した報道ステーションの報道内容は、一般庶民が感じている通りではないか。
安倍首相と政府、そして自民党は、選挙で圧倒的に勝利したのだから好きなようにやっていいと思いあがっているのだろう。だがあの低い投票率の中で議席だけは多数がとれたということであって、決して国民の多数の支持を得たわけではない。むしろ、選挙制度の欠陥によって得た多数議席なのである。そんなことを言っても、安倍首相と自民党は、勝利は勝利だと開き直っている。やはり、選挙の時、有権者がしっかり投票しなければ、安倍首相と自民党を抑えることはできないということだ。(2015.4.14)
(おざわ・としお)
小澤俊夫プロフィール
1930年中国長春生まれ。口承文芸学者。日本女子大学教授、筑波大学副学長、白百合女子大学教授を歴任。筑波大学名誉教授。現在、小澤昔ばなし研究所所長。「昔ばなし大学」主宰。国際口承文芸学会副会長、日本口承文芸学会会長も務めた。2007年にドイツ、ヴァルター・カーン財団のヨーロッパメルヒェン賞を受賞。小澤健二(オザケン)は息子。代表的な著作として「昔話の語法」(福音館書店)、「昔話からのメッセージ ろばの子」(小澤昔ばなし研究所)など多数。