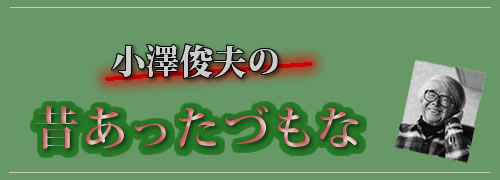【寺田ともかさんのスピーチ】 日時 2015年7月15日(水)
去る7月15日の夜、大阪の梅田で行われた緊急街宣アピールでの、寺田ともかさん(21)のスピーチです。素晴らしいので、「昔あったづもな 第九信」として皆さんに送ります。納得できたら次に伝えてください。若い女性が頑張り始めたのが嬉しいです。スピーチは、IWJ(Independent Web Journal)からの転載です。
日時 2015年7月15日(水)
場所 梅田ヨドバシカメラ前
主催 SEALDs KANSAI
「こんばんは、今日はわたし、本当に腹がたってここにきました。 国民の過半数が反対しているなかで、これを無理やり通したという事実は、紛れもなく独裁です。 だけど、わたし、今この景色に本当に希望を感じてます。 大阪駅がこんなに人で埋め尽くされているのを見るのは、わたし、初めてです。この国が独裁を許すのか、民主主義を守りぬくのかは、今わたしたちの声にかかっています。
先日、安倍首相は、インターネット番組の中で、こういう例を上げていました。『喧嘩が強くて、いつも自分を守ってくれている友達の麻生くんが、いきなり不良に殴りかかられた時には、一緒に反撃するのは当たり前ですよね』って。ぞーっとしました。 この例えを用いるのであれば、この話の続きはどうなるのでしょう。友達が殴りかかられたからと、一緒に不良に反撃をすれば、不良はもっと多くの仲間を連れて攻撃をしてくるでしょう。そして暴力の連鎖が生まれ、不必要に周りを巻き込み、関係のない人まで命を落とすことになります。
この例えを用いるのであれば、正解はこうではないでしょうか。 なぜ彼らが不良にならなければならなかったのか。そして、なぜ友達の麻生くんに殴りかかるような真似をしたのか。その背景を知りたいと検証し、暴力の連鎖を防ぐために、国が壊れる社会の構造を変えること。これが国の果たすべき役割です。
この法案を支持する人たち、あなたたちの言うとおり、テロの恐怖が高まっているのは本当です。テロリストたちは、子どもは教育を受ける権利も、女性が気高く生きる自由も、そして命さえも奪い続けています。 しかし彼らは生まれつきテロリストだった訳ではありません。なぜ彼らがテロリストになってしまったのか。その原因と責任は、国際社会にもあります。9.11で、3000人の命が奪われたからといって、アメリカはその後、正義の名のもとに、130万人もの人の命を奪いました。残酷なのはテロリストだけではありません。 わけの分からない例えで国民を騙し、本質をごまかそうとしても、わたしたちは騙されないし、自分の頭でちゃんと考えて行動します。
日本も守ってもらってばかりではいけないんだと、戦う勇気を持たなければならないのだと、安倍さんは言っていました。だけどわたしは、海外で人を殺すことを肯定する勇気なんてありません。かけがえのない自衛隊員の命を、国防にすらならないことのために消費できるほど、わたしは心臓が強くありません。 わたしは、戦争で奪った命を元に戻すことができない。空爆で破壊された街を建て直す力もない。日本の企業が作った武器で子どもたちが傷ついても、その子たちの未来にわたしは責任を負えない。大切な家族を奪われた悲しみを、わたしはこれっぽっちも癒せない。自分の責任の取れないことを、あの首相のように『わたしが責任を持って』とか、『絶対に』とか、『必ずや』とか、威勢のいい言葉にごまかすことなんてできません。
安倍首相、二度と戦争をしないと誓ったこの国の憲法は、あなたの独裁を認めはしない。国民主権も、基本的人権の尊重も、平和主義も守れないようであれば、あなたはもはやこの国の総理大臣ではありません。 民主主義がここに、こうやって生きている限り、わたしたちはあなたを権力の座から引きずり下ろす権利があります。力があります。あなたはこの夏で辞めることになるし、わたしたちは、来年また戦後71年目を無事に迎えることになるでしょう。 安倍首相、今日あなたは、偉大なことを成し遂げたという誇らしい気持ちでいっぱいかもしれません。けれど、そんな束の間の喜びは、この夜、国民の声によって吹き飛ばされることになります。 今日テレビのニュースで、東京の日比谷音楽堂が戦争法案に反対する人でいっぱいになったと見ました。足腰が弱くなったおじいさんやおばあさんが、暑い中わざわざ外に出て、震える声で拳を突き上げて、戦争反対を叫んでいる姿を見ました。
この70年間日本が戦争せずに済んだのは、こういう大人たちがいたからです。ずっとこうやって戦ってきてくれた人たちがいたからです。 そして、戦争の悲惨さを知っているあの人達が、ずっとこのようにやり続けてきたのは、紛れもなくわたしたちのためでした。ここで終わらせるわけにはいかないんです。わたしたちは抵抗を続けていくんです。 武力では平和を保つことができなかったという歴史の反省の上に立ち、憲法9条という新しくて、最も賢明な安全保障のあり方を続けていくんです。わたしは、この国が武力を持たずに平和を保つ新しい国家としてのモデルを、国際社会に示し続けることを信じます。偽りの政治は長くは続きません。
そろそろここで終わりにしましょう。新しい時代を始めましょう。
2015年7月15日、わたしは戦争法案の強行採決に反対します。ありがとうございました。」(2015・7・22)
参議院で廃案に追い込もう
安倍首相は、議席数だけを頼りに強行採決をした。彼は、国会での審議が進むごとに支持が落ちてきていることに不安を感じたのであろう。新国立競技場の建設計画を修正することを、採決当日に間に合わせて発表したことにも、その不安は表れている。国民の声に耳を傾けていることをアピールしたかったのである。
安倍首相の国会答弁はいつも抽象的で、言葉の中身がない。戦地の場面の説明は稚拙で、とても現代の戦争に通用する想定ではない。そして傲慢である。それにもかかわらず、一定程度の支持があり、選挙になると勝つ。それは何故なのか。安倍政治に反対するわれわれは、この問題を真正面から考えてみなければならないと思う。
安倍首相は「わが国の安全を守ることが、政府の役割だ」という。だが、その「守る」方法は、軍事力ばかり考えている。「後方支援」とか「駆けつけ警護」。そして、「わが国が十分な抑止力を持つことが、相手の攻撃意図をくじくのだ」という。だが、この考え方はまさに「軍拡競争」の考え方である。どの国も、相手が抑止力を増強すれば、対抗してそれを抑止する力を増強しようとする。米ソ対立時代は、まさにこの考え方で軍備拡大競争をしたのである。 だが、国を守る力は軍事力だけではないはずだ。外交力があるはずではないか。一連の国会での論議を見ていると、軍事力の話ばかりだった。安倍首相がホルムズ海峡の機雷の話をしたり、後方支援の話をすると、野党側はそれにつられて、その批判に追われてしまう。軍事力以外で日本を守る論点がほとんど出てこなかった。
「平和国家」として生きていくことを、もう一度確認しよう
日本は「戦争放棄」の憲法を掲げている国である。そのおかげで、世界の諸国、特にアジア・アフリカで、「戦争を仕掛けてこない国」としての安心感を得ている。そして、経済力、技術力、医学力、文化・芸術力で各国の生活安定に寄与している。この「平和力」で他国を幸せにし、自国をも守ることを政治家たちはまともに考えないようである。それは絵空事とでも思っているのであろう。
その「平和力」は、いわゆるアメリカの勢力下にある国ぐにだけでなく、あらゆる国ぐにに及ぼすことができるはずである。これは、「同盟国が攻撃されたら日本への攻撃とみなして攻撃する」という「集団的自衛権」の逆の考え方である。300万人の日本人の命と、3000万人のアジア人の命を犠牲にしてやっと獲得した「平和憲法」を掲げる日本としては、こういう「平和力」を行使すべきなのである。
アメリカから見て敵である国が、皆、日本にとって敵なのではない。そこは落ち着いて、冷静に考えるべきなのである。ロシアはウクライナ問題があるから、アメリカにとって半分敵国である。だが、日本にとっては隣国であり、北方領土問題については友好的に相談していかなければ絶対に希望通りに解決しない。
アメリカは、アフガン、シリア、イラク、イランなどイスラム諸国を引っ掻き回して、収拾のつかない戦乱状態にしてしまった。その悪い結果があの残忍な「イスラム国」である。アメリカが大軍隊でイスラム諸国の国民を苦しめている、その苦しみの中から生まれた残忍な集団なのである。日本は「イスラム国」を含め、怒れるイスラムの人たちと友好的につきあえる国なのである。今まで、援助はしたけれど、攻撃したことはないのだから。その「平和国家」の心棒である「平和憲法」を掲げて、世界に平和を築くことこそ、日本の世界史的役割なのである。
国会審議を通じて、野党もこの大きな観点からの論議を展開できなかったことに、ぼくは失望している。そして、国民の中にも、「国を守るのは軍事力だけだ」という思い込みがあるから、自民党に票が流れるのではないと思う。われわれ国民が、平和憲法の力に自信をもち、「平和国家」として生きていくことに確信を持とう。
われわれの日本を守るのは、軍事力ではなくて「平和の力」なのであることに確信を持とう。そして、政治家たちに「平和の力で国を守ること」に全力を挙げることを要求しよう。それが「戦争法制」を廃案に持ち込む道なのである。(2015・7・22)
(おざわ・としお)
小澤俊夫プロフィール
1930年中国長春生まれ。口承文芸学者。日本女子大学教授、筑波大学副学長、白百合女子大学教授を歴任。筑波大学名誉教授。現在、小澤昔ばなし研究所所長。「昔ばなし大学」主宰。国際口承文芸学会副会長、日本口承文芸学会会長も務めた。2007年にドイツ、ヴァルター・カーン財団のヨーロッパメルヒェン賞を受賞。小澤健二(オザケン)は息子。代表的な著作として「昔話の語法」(福音館書店)、「昔話からのメッセージ ろばの子」(小澤昔ばなし研究所)など多数。