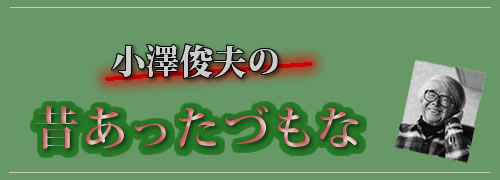世界遺産を蹴って町の生活を守ったドレスデン
昔ばなし大学の「グリム童話研修旅行」のあと「東ドイツ文化の旅」に行ってきた。旅の最後はドレスデンだった。町の中央に壮麗なロココ様式の聖母教会が立っているのだが、この教会、実は先の大戦で連合軍の大爆撃により、完全に破壊されたのである。ぼくが初めてドレスデンを訪れた1989年秋には、この教会は破壊された瓦礫の山のままだった。東西統一後、1991年におとずれた時にもまだ瓦礫の山だった。ドレスデンの友人の話では、現地の人たちはドイツ国民が冒した野蛮な戦争への反省の念と、同じキリスト教徒であるアメリカ、イギリス連合軍が教会を爆撃したことへの戒めとして、瓦礫のままにしてあるのだ、ということだった。
ところが今度行ってみると、教会は完全に修復されて、もとのままの姿になっていた。聞くところによると、修復にあたっては瓦礫の中から各部分の石を探し出して組み立てていったということだった。ない部分はもちろん新しい石で組み立てた。したがって、完成した姿は、爆撃を受けた黒い石と、補った新しい白い石のまだら模様である。それは1998年から2005年まで7年かかった難工事だったそうである。
中に入ってみると、内部は絢爛たるロココ様式が完全に復元されているのには驚いた。だが、もっと驚いて、思わず喝さいの拍手をしたことがある。この旅に同行してくれた、駿河台大学観光学科の小林将輝准教授の説明によると、ドレスデン市とその周辺エルベ渓谷は2004年に、ユネスコにより「世界遺産」に指定された。ところがドレスデン市にはエルベ河を渡る橋が一本しかなくて、下流のほうの住民は対岸に行くには大回りをしなければならなかった。対岸の新市街は発展し、人口が増加したにもかかわらずである。
そこで、現在ある橋の下流にもう一本、橋を増設することになった。これに対し、ユネスコの委員会は、「橋を増設するならば、世界遺産指定は取り消す」と言って脅しをかけてきた。 2006年には「危機にさらされている世界遺産」のリストに登録された。それに対して市長は、橋建設の賛否を問う住民投票を実施した。すると、建設賛成の 票が多数を占めたため、橋の建設は実行された。それに対しユネスコは、2009年、ドレスデンとその周辺エルベ渓谷の世界遺産指定を取り消した、ということであった。
ユネスコという世界機構が古都ドレスデンとその周辺のエルベ渓谷を世界遺産と認定したのに、市民は毎日の生活に必要な橋を選んだのである。ぼくは市民の自我の強さに思わず拍手をした。なんとなく権威のありそうな「世界」よりも自分の生活を大事にする心。
市民の心の中にはきっと「世界機構であるユネスコが認めようが認めまいが、われわれの古都ドレスデンの価値は厳としてあるのだ」という自負もあっただろう。
「世界」という言葉が絶対的権威であるかのように通用している日本の風潮をかねがね批判していたぼくにとっては、喝采を叫びたくなることだったのだ。
日本ではどうだろうか。誰かがノーベル賞を受賞したときのあの大騒ぎ。それは、その研究者の研究内容にたいして賛美するのではなく、受賞したことに対して賛美しているにすぎない。研究は既にあったものなのだから。芸術家の場合も同じだ。世界で認められたとなると大騒ぎする。認められる前から優れた活動をしていたのに、世界が認めると「大したものなのだ」と騒ぎだす。
日本という世間全体が、価値判断を世界に任せてしまって、世界で認められたらいいものなのだと大騒ぎする。「世界」という「中央」が認めたらいいものと思うのだ。
そう考えると、これはしっかり意識しなければならない、大きな、そして根深い問題であることがわかる。どこの民族でも同じ傾向はあるのだろうが、われわれ日本人の間では、「お上」の言うことには逆らわないのがいいこととされてきた。「お上」とは即ち「中央」である。「中央」は自分の権威づけのためにいろいろ な仕掛けを作る。立派な建築物、幅の広い大通り、大きな官僚組織、軍隊など。われわれ庶民はそういう立派なものを見ると、自分とは別世界の、価値の高いものだと思ってしまう。もしその方面からお褒めの言葉が来たら、一も二もなく喜び、舞い上がる。
福島第一原発の大事故を呼び込んだのも、もともとはこのお上意識ではなかったのか。「お上のすることだからいいことなんだろう」と。だが、今、日本中の多くの庶民がこの弱点に気がついいて、お上の出す「戦争法案」を拒否して立ちあがっている。もう「世界」とか「中央」とか「お上」に屈しない強い意識が市民の間にしっかり根付いてきているのである。これを知ったら、ドレスデン市民もきっと拍手してくれるだろう。(2015.8.27)
諦めず、みんな連帯して、これからの選挙でくつがえしていこう
昔ばなし大学再話研究会で那覇に来ている。今、ホテルで参議院本会議を見ている。戦争法案は可決された。だが戦いはこれからなのだ。これまでの議論で、政治権力というものが如何に傲慢で、一方的で、愚かであるかを国民は知ってしまった。国の平和や人々の幸福は自分の政治行動、つまり選挙での投票によってまもらなければだめなんだということをはっきり学んだ。すべての世代が学んだ。選挙での投票が政治を決めていくことを学んだ。来年の参議院選挙では必ず変化を起こそう。みんなで、自分の身近な人々に、今回の戦争法案に賛成した議員を落とそうと呼び掛けよう。各選挙区でも比例区でも。日本はこれまでは平和で当たり前という気分できたが、今回の一連の議論で、平和は自分の選挙で守らなければならないのだということを肌で感じたと思う。諦めず、みんな連帯して、これからの選挙でくつがえしていこう。(2015.9.19 )
開き直って「一億総活躍担当大臣」とは!
彦根、相模、横浜そして田沢湖と昔話の研究会をしてきた。田沢湖では山は紅葉が始まっており、空は澄み渡り、湖水は真っ青ですばらしかった。だが安倍首相は内閣改造にあたり、「一億総活躍プラン」を作るために、その担当大臣を任命したという。聞いて呆れた。 安倍首相が唱えた「日本を取り戻す」とは、「軍国主義日本を取り戻す」だったことがこれではっきりした。
あの戦争を経験しなかった若い人には結びつかないだろうが、戦争中には「一億総動員」とか「一億一心」、「進め一億火の玉だ」、「一億玉砕、本土決戦」と いう言葉が新聞やラジオに毎日書かれ、叫ばれていた。戦争体制そのものを表す言葉なのである。国民一人一人の生活や感情は問題ではない。一億の国民は、自己を捨てて国の一部になれ、そして命を差し出せ、という言葉なのである。その上、1945年の敗戦の時には、「こうなった責任は国民全体にある。天皇に対して申し訳なかった。その意味で一億総懺悔しなければならない」という声が強く上がったのである。
天皇制のもと、国家の支配者たちが、国民を一 塊の道具として使った言葉なのである。そこには、個人の生活とか感情などはそもそも勘定のなかに入っていなかった。個人の自由などと言おうものなら、「危険思想の持主」として検挙されたり、社会から追い出されたりした。あるいは、狙い撃ちされて「赤紙」で軍隊に召集されたのである。軍隊に入れられたら、もう個人の意見は全く言えない。すべては「天皇のご命令」で動く。もちろん実際には天皇が発言するのではなく、一階級上の上官の命令であるにすぎない。だが、絶対に服従しなければならない。「一億」という言葉は、国民をそういう、お上に絶対的に服従する者として把握してきた言葉なのである。
今、安倍首相の口からそれが出てきた。
安倍首相は戦争法案を成立させたと強弁して、これからは国民を勝手気ままに引っ張りまわせると思いこんで、国民を「一億」とまとめたのだろう。だが、そうはさせない。そもそも、あの戦争法案は国会で可決されていない。
次の参議院選挙では、必ず自民、公明党に大打撃を与えよう。落選運動を展開しよう。今から、その準備をしなければならない。(2015.10.9)
(おざわ・としお)
小澤俊夫プロフィール
1930年中国長春生まれ。口承文芸学者。日本女子大学教授、筑波大学副学長、白百合女子大学教授を歴任。筑波大学名誉教授。現在、小澤昔ばなし研究所所長。「昔ばなし大学」主宰。国際口承文芸学会副会長、日本口承文芸学会会長も務めた。2007年にドイツ、ヴァルター・カーン財団のヨーロッパメルヒェン賞を受賞。小澤健二(オザケン)は息子。代表的な著作として「昔話の語法」(福音館書店)、「昔話からのメッセージ ろばの子」(小澤昔ばなし研究所)など多数。