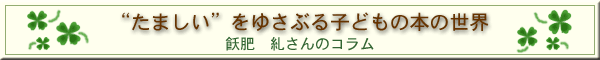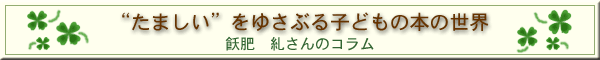|
「絵本フォーラム」第104号・2016.01.10
●●93
人道的正しさを自覚した外交官、ビザを発給へ
『杉原千畝と命のビザ 自由への道』(汐文社)
米人監督チェリン・グラックの映画「杉原千畝」を見る。あらためて外交とは何か、外交官とはどんな仕事かを考えさせられたり、感じ入ったり…。
 大戦下の外交官、杉原千畝の存在を知ったのは、アウシュビッツの写真記録や世界現代史啓蒙書の編纂にかかわっているころだから、恥ずかしながら二十年もたっていない。多数のユダヤ人を死の収容所送りから救った実業家を描くS・スピルバーグ監督の映画「シンドラーのリスト」が上映されたころだったから、千畝を「東洋のシンドラー」と称するメディアがあったように憶う。千畝を中学や高校の歴史授業で扱うようになったのがつい最近のことであり、外務省自身がなんの不都合があるのか、当時、千畝の事績を知らしめようとしていなかった。 大戦下の外交官、杉原千畝の存在を知ったのは、アウシュビッツの写真記録や世界現代史啓蒙書の編纂にかかわっているころだから、恥ずかしながら二十年もたっていない。多数のユダヤ人を死の収容所送りから救った実業家を描くS・スピルバーグ監督の映画「シンドラーのリスト」が上映されたころだったから、千畝を「東洋のシンドラー」と称するメディアがあったように憶う。千畝を中学や高校の歴史授業で扱うようになったのがつい最近のことであり、外務省自身がなんの不都合があるのか、当時、千畝の事績を知らしめようとしていなかった。
外交官であった千畝は、語学堪能で数か国語を操るだけでなく情報収集活動にも長けていた。戦時ともなれば、きわどい諜報戦にも挑む必要があったようだ。日露戦争時の外相・小村寿太郎もそうであったが傑出の秀才も、その才の一部をそんな任務に割かねばならない厄介さを理解したくはないが、想像はできる。
で、まともな人物であれば理不尽さもここにきわまるとなるのが人道的局面だろう。1940年、千畝にもそんな局面が訪れた。独ソの軋轢のあいだで、追われるようにビザを求めて領事館に押し寄せるユダヤ人難民たち。時間の余裕はわずか二週間の待ったなし。千畝がビザを発給しなければ、かれらユダヤ人の死を意味した。ナチスドイツとイタリアにくみして迷走をはじめた本国日本、外務省からの電報は「発給するな
の一点ばり。
領事代理の権限はかぎられていた。が、千畝は悩みぬいてビザ発給を決断する。人道的正しさを省令無視より優先する。うながしたのは、妻であり、子であった。かくして、領事館閉鎖まで、いや、リトアニアを退去する列車乗車直前まで、ビザを書つづける。書きに書く。いくらかなりと役立つなら…と。
絵本『杉原千畝と命のビザ』は、作者が千畝の長男になりかわって当時を想い起こして語るという手法で展開する。そして、セピア色に彩色されたリアリティのある画面の運びは時代性を感じさせて臨場感を与えてくれる。やや美談仕立ての物語絵本ではあるが、子と親とともに読み語ることのできるノンフィクションとなっている。難民問題を大きくかかえる現在、必見の絵本ともいえるのではないか。
それにしても、五年目に入ったシリアの惨状は、ひどい。いつまでつづくかぬかるみぞ、だ。ISというとんでもないテロ集団はゆるせない。しかし、一方の空爆作戦も火に油を注ぐだけではないか。空爆を受ける人々のことをどれだけ考えているのか、怒りだけがつのるばかり。パリのテロ広く世界に報じられ、シリアの人々の日常はあまり伝わらない。四年間で二十万人を超える人々が空爆で殺されたことを知る人は意外にすくない。国によって、民族によって、人間の値打ちに差があるのだろうか。空爆や紛争の力から逃げ出そうというおびただしい数の難民が生まれている。
ドイツをはじめ大量の難民受入れを宣言する国がある。…難民を、移民と同義のように語り、「それより前にやるべきことがある」とするのが、ぼくらの国の立場というのでは、哀しすぎるだろう。かつて杉原千畝が直面した人道破壊の局面は、今また、そこかしこで頻発しているのだ。こんな絵本から学ぶことは多いのである。
「杉原千畝と命のビザ 自由への道」ケン・モチヅキ:作 ドム・リー:絵 中家多惠子
(おび・ただす) |