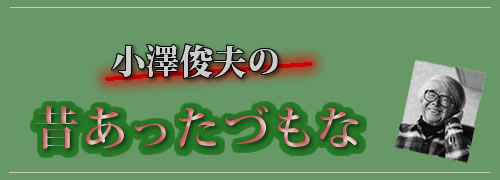野党は統一戦線を組むべきである
今、わが国にとって緊急の課題は、違法な“強行採決”によって“成立”したことになっている一連の「戦争関連法」を廃棄することである。それにはまず、来年の参議院選挙で野党側が勝利しなければならない。 だが、現在の野党側を見ると、バラバラで、このままでは到底自民・公明連合に勝てるとは思えない。ここは、一連の「戦争関連法」を廃棄し、「特定秘密法」を廃棄し、平和憲法を護るという一点で、野党が統一戦線を組むべきである。
新聞報道によると、現在、日本共産党が野党による「国民統一戦線」を呼び掛けているとのことだが、他の野党の反応は鈍いらしい。しかも民主党は、維新の党の分裂騒ぎのあおりを受けて、内部でぎくしゃくしている。国民のほうにも、「共産党」への嫌悪感、ないしアレルギーがあるので、共産党の呼びかけを盛り立てようという雰囲気ではないようだ。
だがぼくは、どの党の主導でもいいから、政治家たちは至急、統一戦線を組み立てるべきだと主張する。そして、国民は、口コミで理解者を増やして、統一戦線の候補者に投票するべきだと、主張する。
1937年(昭和12年)、日本が「事変」と称して、北京郊外の盧溝橋で中国に戦争を仕掛けた時、ぼくはちょうど北京の小学校で一年生だった。日本軍は破竹の勢いで中国軍を蹴散らし、中国は国家的危機に直面した。その時、蒋介石率いる国民政府軍と毛沢東率いる共産党軍は国民統一戦線を組んで日本軍に対抗した。これは「国共合作」として歴史に残っている事実である。
中国という国全体は、この「国共合作」によって日本に勝つことができたのである。日本に勝利した後は、国民政府軍と共産党の八路軍は、改めて本格的な内戦に突入し、最後には八路軍が勝利し、国民政府軍は敗退して、台湾に逃げ込んだのである。
だがとにかく中国としては日本に勝った。日本に勝つことが至上命令だったのである。今、われわれ日本国民にとって至上命令は、安倍政権を倒し、一連の「戦争法」を廃棄し、「特定秘密法」を廃棄し、平和憲法を守ることである。それには、来年の参議院選挙で自民・公明党に絶対多数を取らせないことである。
そのためには、いくつかの野党が、この一点で統一戦線を組むしかない。もしそれを躊躇したら、自民・公明が絶対多数を獲得すること、ほとんど火を見るより明らかである。そんなことを許していいのか。野党の議員たちに聞きたい。絶対に許してはいけないのだ。
「戦争法案」に対してあれだけ強烈に表明された国民の反対意思を、選挙で議席として事実化できるのは政党に属する政治家たちしかいないのだ。国民はそういう議員を作りたいと思っている。政治家たちは、その意思を受けて立ち、実現できるように、舞台装置を準備しておかなければならない。
われわれ国民は、日本の野党政治家たちに、統一戦線を組むことを要求する。(2015.11.19)
違憲状態の国会が違憲の戦争法を強行採決し、議事録は後付けである
これはもうほとんど法治国家とは言えない。しかも、内閣法制局は、内部協議の記録を残していない。日本は今や、歴史が積み上げてきた近代法治国家という枠からはみ出して、中世の独裁的君主制国家になりつつある、といわざるを得ない。
昨日の最高裁判所大法廷は、昨年12月の衆議院選挙は「違憲状態」であるという判決を下した。これは、一票の格差が2.13倍だった小選挙区は投票の平等に反しているとして二つの弁護士グループが選挙の無効を求めた17件の訴訟の上告審判決である。
最高裁が衆議院選挙に「違憲状態」という判決を下したのは、2009年、2012年に続いて、なんと三度目である。
今回の判決に当たっては、裁判官14人のうち9人が「違憲状態」としたが、3人は明確に「違憲」としたのである。「合憲」とした判事も2名いたそうだが。判決では「選挙無効」の訴えは退けた。「選挙無効」となれば政治的大混乱が起きるので、それを避けたのであろう。
最高裁判所が政治的配慮をすることの是非も問題にしなければならないが、国会が「違憲状態」のまま何年も運営されること自体が大きな問題である。国会は、最高裁判所の政治的配慮をいいことに、ゆがんだ選挙制度のもとに成立している現状をフルに活用して、自民党の独裁を進めているのである。自民党は、現状で圧勝できるのだから、選挙制度に手を付けるなど考えもしない。国会の「違憲状態」に支えられて、あの違憲な「戦争法案」が採決されたのである。
ほとんどの憲法学者たちが違憲であると指摘したのに、自民・公明の政府は「違憲状態」の国会であの「戦争法案」を強行採決した。
その上、委員会での記録は、「聞き取れず」なのに、採決は行われたことになっている。記録をこんなに軽々しく扱うのは、民主主義国家としては基本的欠陥である。
「法の番人」の記録隠滅
「記録軽視あるいは無視」行為を安倍首相の政府も平気で行っている。それは内閣法制局である。内閣法制局は法的な側面から内閣を補佐し、首相に意見を述べる政府内の機関で、これまで、内閣の憲法解釈をになってきた。特に憲法九条の規定を守って、自衛隊の海外派遣にたがをはめるなどして、「法の番人」とよばれてきた。
今回の、政府による憲法解釈の変更を巡っては、横畠法制局長官は国会答弁で「法制局内で議論をしてきた」と述べていた。しかし、法制局が内部協議の記録を残していなかったことが判明した。そうなると、憲法についての歴史的な解釈変更に当たって、法制局内でどのような協議が行われたのか、そもそも、解釈変更に異論があったのか、全員一致だったのかという基本的な事実さえ、確かめることができなくなってしまったのである。
朝日新聞によれば、今回の憲法解釈変更にあたって、そもそも記録に残すほどの議論があったのか、という声が法制局内部からも出ているとのことである。集団的自衛権の行使を認める閣議決定案を、自民党の高村正彦副総裁や公明党の北側一雄副代表、横畠氏らによる秘密会合で練っていたという朝日新聞の報道を読んで、内閣法制局のある幹部は、「横畠さんがこの会合に出ていたなら教えてほしかった。知らなかった」と語ったそうである。ある法制局長官経験者も「内部で議論を積み上げた形跡はない。横畠長官一人で判断したようだ」と話しているとのことである。
そもそも現在の横畠長官は、安倍首相が、内閣法制局人事の慣例を破って外部から連れてきた人物である。NHKの会長と同じように、安倍首相のお気に入り人物なのである。横畠長官はその期待に応えて、憲法の解釈変更を認め、しかも協議過程の記録を抹殺したのである。「法の番人」といわれてきた内閣法制局が正当な協議をせず、しかも記録を残さなかったことは、もうこの国は法治国家とは言えなくなったということである。
歴代の自民党政府が守って来た憲法解釈を一内閣の閣議で変更すること自体が、正常な政治行動と言えないが、内閣法制局から変更のお墨付きを得るにもこのような異常な方法を取るとは、安倍首相は民主主義国家の首相ではなくなった。
安倍首相は戦争法案を成立させたと強弁して、これからは国民を勝手気ままに引っ張りまわせると思いこんで、国民を「一億」とまとめたのだろう。だが、そうはさせない。そもそも、あの戦争法案は国会で可決されていない。
日本が平和憲法を護った法治国家であり、民主主義国家であり続けることを願う者は、来年の参議院選挙で自民党、公明党に勝利させないためにあらゆることをしなくてはならないと思う。野党各党にその一点のための統一戦線を要求しよう。そして、その一点を守る候補者に投票しよう。(2015.11.26)
(おざわ・としお)
小澤俊夫プロフィール
1930年中国長春生まれ。口承文芸学者。日本女子大学教授、筑波大学副学長、白百合女子大学教授を歴任。筑波大学名誉教授。現在、小澤昔ばなし研究所所長。「昔ばなし大学」主宰。国際口承文芸学会副会長、日本口承文芸学会会長も務めた。2007年にドイツ、ヴァルター・カーン財団のヨーロッパメルヒェン賞を受賞。小澤健二(オザケン)は息子。代表的な著作として「昔話の語法」(福音館書店)、「昔話からのメッセージ ろばの子」(小澤昔ばなし研究所)など多数。