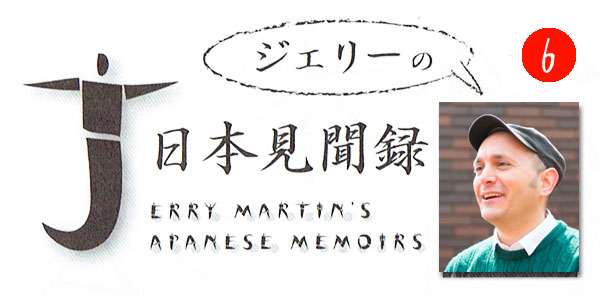『人生の説明書』
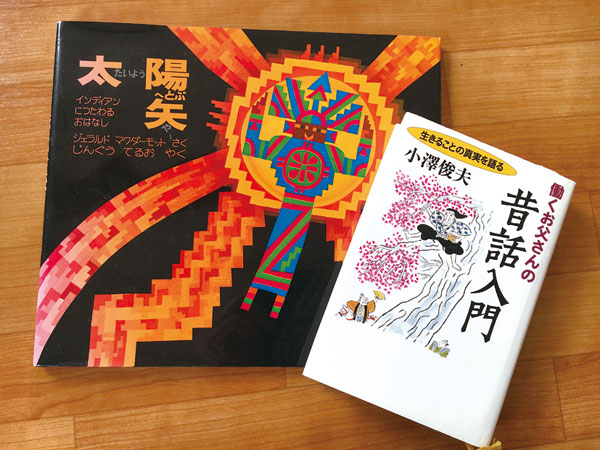 昔話は不思議なものです。名前の通り、昔からあるお話ですが現代の私たちにも響くものがあります。私は子どもの頃、語り部の方々が小学校に来てくれることをとても楽しみにしていましたし、自分でも昔話をたくさん読みましたが、一歩ずつ大人の階段を登るにつれて、昔話の世界から遠ざかってしまったような気がします。「絵本講師・養成講座」を受講している時に最後のレポートを書くためにたくさんの昔話を読みました。私の昔話に対するイメージを変えたのは小澤俊夫先生の『働くお父さんのための昔話入門』でした。名前がとても長い本ですが、伝えたいことは簡単です。昔話は現代にも十分通じるし、もっと身近なものであるべきだということです。
昔話は不思議なものです。名前の通り、昔からあるお話ですが現代の私たちにも響くものがあります。私は子どもの頃、語り部の方々が小学校に来てくれることをとても楽しみにしていましたし、自分でも昔話をたくさん読みましたが、一歩ずつ大人の階段を登るにつれて、昔話の世界から遠ざかってしまったような気がします。「絵本講師・養成講座」を受講している時に最後のレポートを書くためにたくさんの昔話を読みました。私の昔話に対するイメージを変えたのは小澤俊夫先生の『働くお父さんのための昔話入門』でした。名前がとても長い本ですが、伝えたいことは簡単です。昔話は現代にも十分通じるし、もっと身近なものであるべきだということです。
小学生の頃、学校に来てくれる語り部の中にネイティブアメリカンの方もいました。子どもたちがネイティブアメリカンの文化をもっと知るためにネイティブアメリカンの昔話を語ってくれました。別の語り部や劇団グループもよく来てくれましたが、私はこのネイティブアメリカンの語り部の方が一番好きでした。音楽もなし、大げさな事もなく、マイクも使わず、はっきりした生の声の語りでした。その方のおかげで『たいようへとぶや』という話に出会いました。その方は毎回この話をしてくれました。私はこの絵本版があることを知らなかったのですが、「絵本講師・養成講座」の講義の中で再会し、とても不思議な感じがしました。小澤先生の本とこの絵本のおかげで私はまた昔話の世界に戻ることができました。
養成講座を卒業して、小澤先生の本の虜になってしまいました。民話、昔話、伝説、神話の違いから、3回くり返すことの大切さまでスポンジのように吸収しました。小澤先生の「むかしばなし大学」が東京に来た時には迷わず入学し、3年間昔話について深く勉強しました。語り部の方、昔話好きの方、小澤先生のファンの方、色んな方々と一緒に勉強しました。昔話の文法からグリム兄弟まで幅広く、たくさん勉強しました。卒業した時、私の昔話についてのスタンスはすごく変わりました。昔話はただの面白い話ではなく、人生の説明書なのだと気づきました。
お年寄りを敬う、動物に優しくする、人の話をちゃんと聞く事の大切さなどを昔話から学ぶ事ができます。人生に役に立つ事を子どもに教えるのはなかなか難しいと思いますが、ジャーナリストのむのたけじ氏が養成講座の講演の時にこう言いました。「学びにおいて、誰かの真似をすることも必要です」。人から真似る事もできますし、物語から真似る事もできると思います。なので、昔話や絵本、また、語り部から……。様々な方法で、子どもにたくさんの物語を届ける事が大切だと思います。
また、リテラシー(読解記述力)の専門家メム・フォックス氏の話によると、一般的に子どもは一人で読めるようになるまでにおよそ1000の物語を聞く必要があるそうです。そうすることで母国語に必要な音を全部学ぶことができ、同時に家族間の絆を築くためのコミュニケーションの時間にもなります。
人間社会はだんだん便利になるにしたがって言葉の量が少なくなっている気がします。テレビやゲームの時間が増えると、目を合わせながらのコミュニケーションの時間が減ります。コミュニケーションが足りなくなると先ほどリストアップした人生に役に立つ事(お年寄りを敬う、動物に優しくする、人の話をちゃんと聞くなど)が伝わらなくなってしまいます。最近、昔話を知らない未成年者が犯罪を起こした後に「なぜ罪を犯してしまったか」という問いに対して、「何が起こるか知りたかった」という返事が返ってきたそうです。普通に考えると想像は出来ると思います。昔話をあまり知らないから想像出来ないのでしょうか? この子どもたちのリハビリの中に、昔話を読む授業があるそうです。
昔話の説明書はとてもいいものですが、ただテーブルの上に置くのではなく、子どもと一緒に読むということが一番大事です。この説明書と共にたくさんの人たちとコミュニケーションをとり、子どもたちが真似をしても恥ずかしくないように、私たち大人は頑張らないといけないと思います。
(ジェリー・マーティン)