 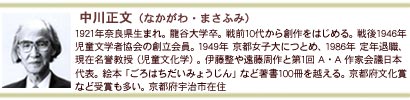 |
|
− 18 − 灯をともす人の高さに灯をともす |
|
わたしは、ひとの言葉に感動して、息がつまるほど深い思いに打たれることがあります。 高きに灯ともす 人間の高さにともす という河井寛次郎に出合ったときもそうでした(火の誓い・講談社文芸文庫)。人間国宝や文化勲章に推されたときも応じないで、ひたすら陶工として「灯をともす 人の高さに灯をともす」と生涯を送った、この人の生き方から、どれほど多くのことを学んだことでしょう。 子どもと文化、そして子どもと絵本とのかかわりを考えるときには、いつも、この言葉がわたしのめざす行先を示し、わたしの仕事が支えられていることが、自分でもわかりました。 つまり私たちの言葉でいうならば、絵本を考えるにあたって画家は芸術にかかわるものとして、情熱と技術のすべてをこめて優れた絵を描きあげるのは当然として、また画家自身、ひとりの人生の先輩である限り、自分の絵が子どもたちにとって、どういう意味をもつか、という責任を感じてもらいたいということになります。 そこが成人専用の芸術と違うところです。そして芸術家としての画業が、子どもたちの成長に役だつという自信をもち、そのために何を伝えなければならないかを、画家としての精進の、もうひとつの重要な柱にしなければならないでしょう。 良心的な絵本の画家たちは、いつもその二つの側面のバランスに悩み、苦しんでいるようですが、そういう自覚や省察の全然ない画家、ただ永年の技術だけで、とにかく一応の絵本の絵を描いて生計を保っている人びと、その他、子どもに何が必要かではなく、子どもがテレビやマンガに飛びつくと同じような種類の絵を平気で垂れ流している画家が、それらの人びとにそういう絵を要求している編集者、そしてそういうものが子どもが喜ぶから子ども向きだと考えて、それらを無自覚に買い与えているのんきな親や先生たち、それらがよってたかって絵本産業を支えている現在の出版事情。 現代のわが国は、一方で歴史的にも芸術的にも目が覚めるほど優れた絵本が続出して、互いに競いあっていると同時に、それ以上の「子どもにとどけたくない絵本」が大量にハンランしているのです。 ■はじめての出会い はじめに河井寛次郎の言葉に感動したと書きましたが、それは子どもの背丈けの高さに灯をともす、で終らずその灯こそ人間として灯ともす、人間らしい成長と発達とを目ざすことでもありました。 蓮如上人は「ご一代記聞き書」のなかで、自分と弟子とは「平座」でつきあえと語っているように、私と絵本と子どもとの基本的な関係は、絵本を中だちにして、おとなと子どもが同じ経験をすること、つまり成人は読み手として絵本につきあい、子どもたちは読んでくれる成人が感動した同じ絵本を共に感動する。そして人間として「共に成長」するものと理解してきましたが河井の「灯ともす」内容とは全く同じ趣旨であることに、近ごろ、いよいよ強く感じるようになりました。 「共に成長する」といい「灯ともす」ためには、当然子どもを、子どもの成長のプロセスを考えなければなりません。子どもたちにも文章のように、さまざまな刺戟を経て理解できるのではなく、一パツで誰もが同じものを捉える絵をとおし、絵を媒介とした「絵本はいかにあるべきか」をこのあと明らかにしたいと思っています。 まず、子どもたち、最初いつどのようにして絵本とであうのでしょう。 いま、注目されているブックスタートという運動が全国に拡がっています。わが国では生後2カ月〜4カ月目くらいに、それぞれ地域の保健所で乳幼児健診というものを受けるわけですが、その際少くても2冊の「赤ちゃん絵本」をかわいい袋にいれて「公費」でプレゼントするというものです。この活動のすごいところは、これまで家庭にまかせていた絵本との出会いを、地域で経費をだして支えるということです。その活動は、1992年イギリスのバーミンガムではじまり、わが国でも十年ほど前に移入されて、あっというまに多くの地方公共団体が開始、日本の絵本事情を革命的に変えたもので、2、3カ月目の子どもが、その絵本にちゃんと反応することが、わかって、お母さんの意識まで変わってきたくらいです。 私はそういう絵本にかかわるプラスの面を、たいへん有難いものだと胸をワクワクさせていますが、ブックスタートを絶対的に応援しながらも、個人として少々危惧をもっています。 それは「2カ月や3カ月では遅すぎる、妊娠したら絵本を読もう」というキャンペーンを始めたのですが、これには「わたしなりの仕掛け」を踏まえた上のことです。(つづく) |
「絵本フォーラム」52号・2007.05.10
前へ ★次へ
