 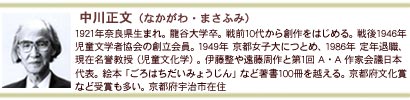 |
|
− 29 − |
ふしぎなものです。わたしなど小学校で習い覚えた唱歌は、すでに八〇年もたつのに、机のまわりを整理したり、ちょっとした探しものをしているとき、つい自然に鼻歌で歌っているのです。 それが「われは海の子」であったり「大こくさま」「村祭」など沢山ありましたが、どういうわけかいつのまにか「二宮金次郎」になって、——手本は二宮金次郎…を繰り返しているのです。 わたしなど、そういう事態を驚くと同時に二拍子の調子の強さ、それに子ども時代のインプリンティング——「刷り込み」の根の深さ、したたかさを思い知らされるのです。 そしてその場合の歌詞をしっかりと確かめると、「手本は二宮金次郎」と結論づけるだけの徳目が、ちゃんと揃っているのです。一番を点検するとよくわかりますが、「柴かり」や「縄ない」「わらじつくり」などがずらっと並び、最後の行の「手本は、なるほど金次郎」だと納得できるように仕掛けています。つまり原因があり、それが直接結果となって歌いあげる、結果をもたらすために、他のややこしい状況が何もない!という単純明解な論理で進行する説得力でもあろうと思われます。この強い構成が子どもたちに刷りこまれ、いつまでも忘れられないものにしているようです。 なぜこんな二宮金次郎をもちだしたか、というところに、幼児向物語の大切なポイントがあると考えているからです。その代表的なものが『もりのなか』エッツの世界の構図というわけです。 エッツの主人公「ぼく」は特別の仕掛けのない帽子をかぶった子どもです。その子どもがラッパを吹きながら森の中に散歩にでかけます。 すると次々に動物たちに出合います。たとえば最初の動物はライオンですが晝寝をしていますし、それが目をさまし、自分の方から「ぼく」にアッピールしては髪をとかしたうえ「ぼく」の最初の同伴者になります。 そして二番目のぞうの子どもが水あびをしています。その子ぞうが「ぼく」を発見し、仲間になって行列の散歩に加わります。こうして子ぞうに引きつづいて茶いろの熊、それからカンガルーというわけでやはり行列に入ります。それから、こうのとり、二ひきのサルなどあらわれ、うさぎまで集団の中へ入っていきます。この登場人物は、これまですべて関係のないもので、しかも、どちらが重要であるか、またどちらが行列のあとか先かなどというのはバラバラで、そんな詮索などは不必要です。つまりこの時期の子どもたちは、場面での一貫性、つまり人物間の相互関係や登場の条件をこえ別々の姿を見せます。 一貫しているのは両方とも「ぼく」の進行と動物たちの参加だけというルーズな組み立て。それは「二宮金次郎」の一行から三行までの個々の徳目のややいい加減な羅列と、そっくりではありませんか。 そういう金次郎のあれもこれもという程度の体系のない徳目の並べ方のルーズさ「手本は二宮金次郎」という強力な文言につなげる現実を超えた論理、それも「もりのなか」の前半のまるで自由なストーリーの展開、そして個々の動物たちが過去の経緯を共に原因とすることなく、終幕につづく集団遊びに統一される。 これが「手本は二宮金次郎」さまざまの徳目が集約されるという構造と全く同じような似た特徴が、幼児の理解力に適応した、忘れられない物語の命脈を保っては、絵物語の名作として命脈を保ってきたようになったのだと思われます。 しかし、ただ二つのものに共通するパターンには、終結部分で共に一応解決したように見えますが、このあとどうなっていくか。また金次郎の方も、このあとの生涯とどのように繋がっていくか、更にまた「もりのなか」の「ぼく」の前に突如あらわれて「ぼく」を現実の世界に引き戻したと思われる父親と「ぼく」との関係とが将来どのように展開をするかを明確にしていません。こんな共に暗示すらない不安定な迷いを残して二つの作品は終るわけですが、ひょっとすると、共に対象が幼児向であり、その点でも幼児向専用の物語であるかもしれません。 |
「絵本フォーラム」63号・2009.03.10
前へ ★ 次へ
