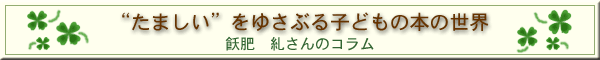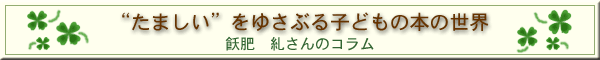|
「絵本フォーラム」第87号・2012.03.10
●●76
大地をよみがえらせた男の孤独な精神とは
『木を植えた男』
 昨年末から年初にかけて京大山中教授のノーベル賞受賞の話題で持ちきりとなる。「成熟した細胞を初期化して万能な状態に戻せることの発見」が授賞理由で、いわゆるiPS細胞が移植再生医療への道を開いた。重篤な難病に苦しむ人々にとって朗報であり、期待は過熱する。柔道やラグビーに熱中した学生期、自らを飽きっぽい性格だとして、スタッフとともに研究がつづけられたことをけれん味なく語る山中教授。陽性の人柄が過熱報道に重なった。天才だって他の力を活用しなければそう容易には傑出した業績を積み上げられないだろう。いずれにしても金字塔、喝采したい大きな業績である。 昨年末から年初にかけて京大山中教授のノーベル賞受賞の話題で持ちきりとなる。「成熟した細胞を初期化して万能な状態に戻せることの発見」が授賞理由で、いわゆるiPS細胞が移植再生医療への道を開いた。重篤な難病に苦しむ人々にとって朗報であり、期待は過熱する。柔道やラグビーに熱中した学生期、自らを飽きっぽい性格だとして、スタッフとともに研究がつづけられたことをけれん味なく語る山中教授。陽性の人柄が過熱報道に重なった。天才だって他の力を活用しなければそう容易には傑出した業績を積み上げられないだろう。いずれにしても金字塔、喝采したい大きな業績である。
それでは、たったひとりで何事かを為すことは不可能なのか、と、ぼくは考えてしまう。
たとえば、絵本『木を植えた男』のエルゼアール・ブフィエはどうか。仮想の人物だが実在してもおかしくない。一人息子と妻を失い世間から身をひいた男は、羊と犬を伴侶にたったひとり南仏プロヴァンスの荒地に住む。不思議なことに男は孤独な生活に喜びすら感じているという。さらに男は何かためになる仕事をと木を植えはじめるのだ。「木のない土地は、死んだも同然。よき伴侶を持たせなければ」というのが男の思いだ。不毛の高地に何十万個もの種を植えつける。育つのはせいぜい10分の1で、ときに全滅する。それも名誉も報酬ももとめない。30年という気の遠くなるほどの年月を、こんな無償の仕事にうちこむのである。これが孤独な男の考えることだろうか。
作品は、旅人の若者が荒れ地で出会ったブフィエについて語る重厚な感動物語だ。時代設定は20世紀初頭の南仏プロヴァンスの荒地。物語を映像フレームのように展開させる絵画の強い力も見のがせない。
水を失った若者がブフィエと遭遇し男の家に泊めてもらうことに。男ほとんど口を利かない。「孤独な人とはそうしたもの」とは若者の勝手な得心だが、ぼくはブフィエを単なる孤独な男ととらえることはできない。
ブフィエは廃屋だった家をみごとに修理し、部屋も調度も清楚にかたづけていた。身なりも清潔で整えている。犬までが男同様で静かで人あたりがやわらかい。口数こそ少ないが男の若者への対応はおだやかで気持ちよい。連泊を願う若者にもまったく迷惑がることがない。こんなブフィエを果たして孤独な生活者とよんでいいのだろうか。男は犬や羊を、そして自然を人生の同伴者として認めていたのではなかったか。
苦労して植えつけた種を全滅させて絶望の淵にも立ったことも永い年月の間にはあるというブフィエ。しかし、男の精神は屈することなく、大地と対話しながら翌年にはリベンジする。ともかくも、男は木を植えつづける。その間、勃発した二つの世界大戦は各国各地を破壊する。そんなことに屈しない男はなおも植えつづけた。
結果は語るまでもない。かつての荒地は広大な森となり、清水がとうとうと流れる水路も生まれ豊かな田園も広がった。大地は生命をよみがえらせたのだ。
戦争から帰還し再びブフィエを訪ねるようになったかつての若者は「戦争という、途方もない破壊をもたらす人間が、他の場所では神のみわざにひとしい偉業をなしとげる」と驚嘆するばかり。そうなのだ、すべての功罪は人間に因る。心しておきたい理だろう。
孤独とはどんな精神性なのか。負の側面で語られることが多いが、肯定される側面も多く語られていいと思う。
『木を植えた男』
( ジャン・ジオノ /原作、フレデリック・バック /絵、寺岡 襄 /訳、あすなろ書房 ) |