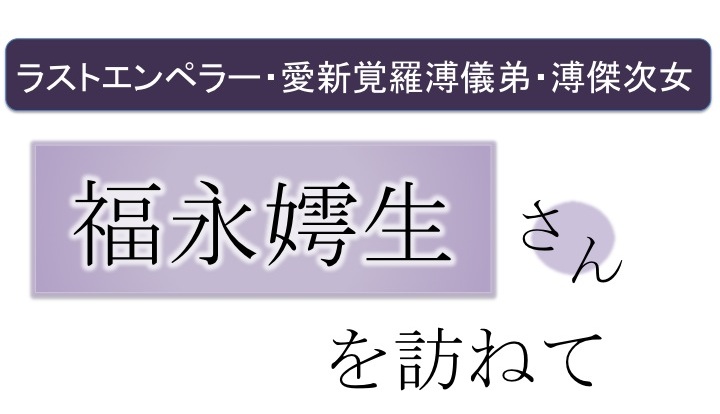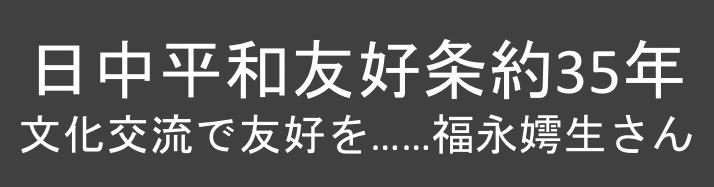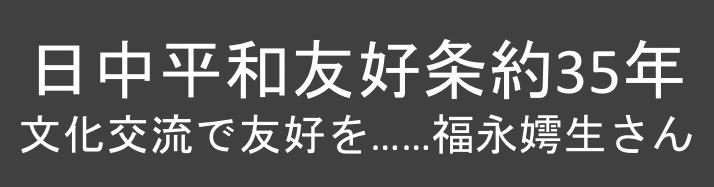
風薫る5月14日、西宮市の福永嫮生さんのご自宅を、写真担当の原知恵(芦屋7期)と共にお訪ねしました。街が一望できる素晴らしい眺望の居間のテーブルには、私たちの到着時間に合わせて冷たいおしぼりと茶菓が置かれ、春風のような微笑みで私たちを迎えてくださいました。今日は、北京での生活と料理、子育てについてお聞きします。
おもてなしの気持ち楽しむ
—— 素敵な食器でございますね。
お人がよくお見えになるので「あればよいでしょう」と娘が買ってくれた物でございます。
—— ご両親様のお住まいのお庭には果樹や草花が多く、お母様も確かお客様が多い生活で,料理がお得意でいらしたそうですね。
はい。両親が晩年住んでおりました北京の護国寺の家の庭には果物の木が多く、果実が稔る前に花が咲くのが綺麗で、父も母も木や花が大好きでございました。朝の水やりは父が、夕方は母がやっておりました。木々や草花は人の心を和(なご)ませてくれますでしょ。 
お客様がいらしても花が咲いておりますと、夕方お庭に大きな丸いテーブルを出して打ち水をしてそこに母が作ったご飯をお出ししておりました。
当時は配給でなかなか材料を手に入れるのが困難でした。が、たった一丁のお豆腐からでもいくつかの前菜が出来るのでございます。
本当にお客様に対して、自分の手で料理を工夫しておもてなしをすることを楽しんでおりました。母が元気な間は、いつも庭から母の笑い声が絶えない北京での生活でございました。
中国の夏は暑いのでお昼休みに一時間程お昼寝の時間がございます。父はそのお昼寝の時間を返上して購買部のような所で珍しい材料を買ってバスに乗って母に届けていたようでございます。
—— お優しいですね。袋を下げたお父様のお姿が目に浮かぶようでございます。お母様は、料理の本をお出しになっていらっしゃいますが。何かお母様の思い出のお料理を一品お教えいただけますでしょうか。
これが婦人画報社から母が出しました『食在宮廷』(注1)という料理の本でございます。もう絶版になっておりますが、今、日本では学生社から「『食在宮廷』〈増補新版〉中国の宮廷料理」(注2)が出版されています。
思い出の料理、色々ございます。一品というとなかなか難しいですね(笑い)。
夏になりますと、レタスを皮にして、その中に紫蘇の葉を一枚入れて胡麻だれをぬって、その上に色々な野菜や卵、ベーコン、ハムの入った塩こしょう味の炒飯を入れていただく菜包という料理がございまして、ビールを飲みながら召し上がると皆さんに大好評です。
子どもは皆の中で育つ
—— 美味しそうでございますね。是非、作ってみたいと思います。お母様から受け継がれたお料理のように、子育てについても受け継がれたことは何かございますか。
私に子どもが出来たとき、母からの手紙に「子どもは可愛いでしょうけれど、おもちゃをたくさん与えないこと。日本はいくらでも物はあるでしょうけれど、一つの物で工夫をして遊ばせないと気が散って移り気な子どもになると将来可哀想なことになるから、最低限で工夫してずっと遊ばせるように」、と手紙に書いてくれました。また「お稽古の中から身に付くもの、資格を取るように」「健康でさえあれば資格があったら恐らく生活には困らないだろうから」、とも手紙に認めてありました。
姉はバイオリンを、私はピアノを習っておりました。母もかつて著名な先生にピアノを習っておりましたので、ピアノが弾けます。これくらいは弾けるだろう、と思っているところを私が何回も間違って弾くと、ピシャと叩かれるのでございます。どんなことがあっても、一日四時間くらい練習をしないと叱られました。その内ピアノの前に座るのが怖くなったくらいでございますが、母にしたら、芸術なら芸術を身につけて食べていかれるように、と必死の思いで私たち子どもを育ててくれたのだろうと思います。
「共産国であっても芸術に国境はないから」、と申しておりました。怖かったのでございますよ、ピアノ(笑い)。
私共が弾いていたピアノを、嵯峨の叔父の子どもたちも弾いておりました。間違うと子どもたちもお母さんに叱られていたらしくて、叔父が「このピアノは祟っていて、怖いね」、と冗談を言うほど熱心だったようです。
主人の母は上の子が夜寝る時、必ずお話をしたり絵本を読んだりしてくれましたが、おばあちゃまが先に寝てしまって(笑い)。
主人も子どもたちに自分で作ったお話をして寝かしておりました。自分で作るから次の日にお話が少し変わっているのです。「ちがうよ!」、と指摘されたりしておりました。
〈尾の白い仔猫の話〉なんかもしたようです。「面白かったか?」、と聞いて『お(尾)もしろ(白)かった』、と笑い、ことばをかけて楽しんでいたようでございます。
主人が亡くなった今、子どもたちが「お父さんは子煩悩で、いろんな話をしてくれた」、と電話で懐かしそうに話しております。
このようなことが大事なことでございます。
お話や絵本の読み聞かせをすることが、後に国語力がついてくるようでございます。何でも基礎は国語でございますから。問題の文を読み違えてはたいへんでございますから。小さい時のことばがけはこどもの成長の基礎だと思います。
—— 今、乱暴なことばや相手を責めるような強いことばをよく耳に致しますが、嫮生さんはどのようにお感じになられますか。
ある程度、理性や教養というのは、学ぶことで身につくことだと思っております。
やはり、ちゃんとした敬語は、家庭で教えるべきだと思うのですよ。子どもは無限の力がありますから、将来どんなに偉くなって、偉い方とお付き合いをすることもあるかも分かりません。
お箸の持ち方など、最低限のことは教えてあげないと恥をかいたら可哀想ですから。家庭で教えるべきだと思っております。
—— 五人のお子さんを育てられた嫮生さんから、今、子育てをされているお母さん達に何かおことばをいただけますでしょうか。
一人で苦労してイライラせずに、人はそれぞれ性格が違いますから、いろんな方と話し合っていろんなお子さんと遊ばせたりしていると自然に一人で悩むこともなくなって上手く育てていけると思います。
そして子どももそれぞれ性格が違いますから、同じように育てても違って参ります。
その子その子の良いところを見つけてあげて褒めて伸ばしてあげるといいですね。怒ってしまうと縮んでしまうので褒めて育ててあげる。子どもは褒められると伸びます。
頭を撫でられると嬉しそうにします。子どもはまた頑張ろうとします。褒めて育ててあげてください。
—— 頭を撫でるお母さんは笑顔ですから。子どもは、お父さんお母さんの笑顔が大好きです。
はじめての子どもは、良く育てようと親も必死に頑張りすぎたりするものです。だからすぐ怒ったりしてしまいます。
でも後の子は、一緒に生きられる時間が短いと思うと余計に可哀想になり、優しくなってしまうものです。一緒にいられる時間が少ないと思うと意識していなくても怒るのが少ないようです。
親子が共に生きる時間は限られています。命がけの流転の日々を経験されたからこその思いでしょうか。だからこそ嫮生さんは人にも優しく穏やかなのでしょうか。次回は、ご両親と嫮生さんの生き方・日々の思いなどをお聞きしたいと思っています。
(ないとう・なおこ)
(注1)『食在宮廷』(愛新覚羅 浩/著、婦人画報社)絶版
(注2)『食在宮廷』〈増補新版〉中国の宮廷料理(愛新覚羅 浩/著馬遅伯昌料理校/訂、学生社)(現在増刷中)
|