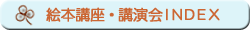| メディアとどう付き合いますか? |
今日、皆さんがいきなり「抱っこして本を読んであげる」と言ったら、お子さんはどんな反応をするでしょう。「いやだ」「何を考えているんだよ」「何か企んでいるんじゃないか」、子どもは様々な反応をするかもしれませんが、本当に親子の心をきちんとつないでいく作業は、そういうところから始まっていかなければいけないのです。そして、そういうものが現在の子育ての中では、なくなってしまっているのです。その一番の原因は、社会の構造変化でしょう。最も大きな変化は、家庭の中にいろいろなメディア、電子機器が入ってきたことです。そして、その最たるものがテレビなのです。 小学校1年生から3年生ぐらいの子どもが、テレビを毎日1〜2時間見ることは問題ないと、学者は言っています。しかし、1歳から3歳ぐらいの子どもが1日4〜5時間テレビを見ていたら、確実に人間が壊れていくと言われています。しかし、今はそういう子育てが増えてきているのです。
小学校1年生から3年生ぐらいの子どもが、テレビを毎日1〜2時間見ることは問題ないと、学者は言っています。しかし、1歳から3歳ぐらいの子どもが1日4〜5時間テレビを見ていたら、確実に人間が壊れていくと言われています。しかし、今はそういう子育てが増えてきているのです。これからは学校の先生にも注意して聞いていただきたいのですが、日本語を使わない子育てが、ものすごい勢いで増えてきました。日本語を使わない子育てとは、どういうものでしょうか。起きているときには英語のビデオを見せ、眠っているときには耳元で英語のカセットを聴かせる。つまり、子どもの脳がまだ柔らかい時期に、外国語を覚えさせておこうということで、極力英語づけの生活を送らせるということです。これは確かに効果のあることだと言われています。しかし、母国語である日本語を習得できないということは、親と子の関係性を断絶しているのだということに気づかなければ本当はいけないのです。 でも、お母さんにしてみると真剣です。バイリンガルにするんだ、国際的に通用する人間に育てるんだということで、一生懸命です。もし私の言っていることがオーバーだとお思いであれば、インターネットを使える方は一度、「英語で子育て」と打ち込んで検索してみてください。びっくりするぐらいたくさん出てきます。現在、このような恐ろしい子育てが蔓延しているのです。 小学校で英語を教えるということを責めているわけではありません。小学校1年生の担任、あるいは保育園、幼稚園の先生は、英語を十分知っておかないと、入ってくる子どもたちに対応できないということが、近未来に出てくる可能性があるのです。それはすなわち、人間性を壊された子どもたちがどんどん出てくる危険性があるということです。 「メディアリテラシー」という言葉を聞かれたことがあると思います。テレビやビデオ、パソコンなどのメディアとどうつきあっていけばいいのかということです。「テレビは絶対的な悪ではなく、つきあい方によっては、いいものです。こんなつきあい方をしましょう。こんな見方をしましょう」という考え方がメディアリテラシーです。そういうことを一生懸命やっている清川輝基という方が、ついこの間本を出しました。NHK放送文化研究所の専門委員で、慶應義塾大学の講師もされている方です。本のタイトルは、『人間になれない子どもたち−現代子育ての落し穴−』(エイ出版社)です。 「大人になれない子どもたち」という言葉はよく聞きます。例えば、成人式を20歳でするより30歳でするほうが、現実の子どもの成育には合っていると言う学者もいます。私もどちらかというと、25歳ぐらいでもいいのではないかと思います。そのようにだんだん成長が遅れてきていることを指して、「大人になれない子どもたち」と言っています。しかし現在、メディアの弊害によって、人間にさえなれない子どもが増えてきたということなのです。 |
| 人間になれない子どもたち |
|
そして、2歳までの子どもには絶対にテレビやビデオを見せてはいけません、百害あって一利なしと言っています。そう言うと、テレビがもともとある生活環境の中で育ってきたお母さん、お父さん方は、「そんなことはない。私だってテレビをずーっと見てきたけれど、まともだ」とおっしゃいます。まともかどうかは置いておくとして(笑)、先ほど言いましたように、そのときと今とでは社会の条件が大きく変わっています。今、子どもにテレビを見せ続けることで、様々な問題が起こってきているのです。 わかりやすい肉体的、身体的な例から挙げていきます。まず、目が悪くなります。これは常識ですね。これは1歳、2歳の話です。小学校高学年のお子さんになると、ちょっと話は違いますが、まず目が悪くなるということがあります。 それから、背筋力が育たないということです。背筋力とは、ものを持ち上げる力のことです。若いお母さんで、自分の赤ちゃんを抱くのに必要な背筋力さえ育っていない方が増えてきているのです。文部科学省が学校の体力測定で背筋力も測定していたのですが、6年前に中止しました。背筋力の測定をすると、「腰が痛い」と言って学校を休む子どもが続出したのです。それで中止する文部科学省も文部科学省ですが、そういうものが出てきました。 もう一つは、自律神経が育たないということです。子どもは、動き回って汗をかいたりしながら、自分の身体を自分で調節していく自律神経をつくっていきます。しかし、1〜3歳ぐらいの子どもをテレビの前に4時間も5時間も座らせておくと、自律神経をつくることができなくなってしまうのです。肉体的、身体的な面では、そういう例があります。 さらに恐ろしいことがあります。これは片岡直樹という川崎医科大学の小児科の教授が言っているのですが、最近、子どもたちに新しい症状が出てきました。テレビを見せていたら、子どもは集中しているから、言葉などを早く覚えるというのは大嘘である。テレビやビデオを見せたり、ゲームをさせておいた子どもには、自閉症類似の症状が現れる。彼はそうはっきりと言っています。自閉症はれっきとした病気です。お医者さんにかかって治療をしなければいけないものなのですが、それと同じ症状を現す子どもたちがどんどん増えてきているのです。 また、子どもの言葉の獲得についての問題もあります。子どもは半年か1年ぐらいの間に喃語が出て、早い子で1歳から1歳半、ちょっと遅れたとしても2歳で初語を発することができます。ところが、3歳になっても言葉が出ない子どもが増えてきたのです。これは、テレビやビデオをずっと見せ続けていたことが原因だとされています。このような新しい形の言葉の遅れが、子どもたちの中に蔓延してきているのです。 もう一つは、脳科学の分野からの警告です。今まで、脳科学の分野が子育てについて発言することはあまりありませんでした。しかし今、子育てに対して最も真剣に発言し、警告を発しているのです。つまり、メディアの害を直接受けているのは脳だということがわかってきたのです。テレビやビデオを見続けたり、ゲームばかりやっていると、前頭葉が発達しなくなります。前頭葉とは、うれしさや悲しさ、楽しさやつらさなど、いろいろな感情を司っている部分です。それが発達しない子どもが増えてきているという警告が、脳科学の分野から発せられているのです。 アメリカでは約20年も前から、2歳以下の子どもにはテレビを見せてはいけないということが言われていました。コンピュータを使って授業した子どもと、コンピュータを使わずに授業した子どもとの比較など、メディアが子どもたちに与える影響について様々な実験が重ねられており、様々な分野で多くの人たちが警告を発しています。日本ではようやく、「2歳までは見せないほうがいいよ」「できるだけ見せないでください」と言われ始めたところです。 我々大人が1日中テレビを見たって、ほとんど害はありません。次の日に眠くなるとか、疲れるということは起こるでしょうが、それ以上の症状が身体や精神に現れるということはほとんどないのです。しかし、生まれてほんの1〜2年の子どもたちが、テレビやゲーム、パソコンなどの電子映像メディアから受ける影響は恐るべきものです。これは、子育てをしていく中でしっかりと考えなければいけないことだと思います。 |
| 読み聞かせはだれのため? |
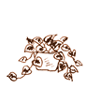 そこでやはり、本を読むこと、絵本に接することがとても大事になってきます。学校や家庭で、子どもたちに絵本を読んであげるという活動をしていかれたらいいと思います。今、日本全国で読み聞かせや読み語り、アニマシオン、ストーリーテリング、ブックトークなど、絵本をめぐる様々な活動が行われています。ただ一つ問題なのは、かつての文庫運動の悪しき側面と同じものを読み聞かせのボランティアの方が持っていらっしゃるという点です。私は、これを大変危惧しています。
そこでやはり、本を読むこと、絵本に接することがとても大事になってきます。学校や家庭で、子どもたちに絵本を読んであげるという活動をしていかれたらいいと思います。今、日本全国で読み聞かせや読み語り、アニマシオン、ストーリーテリング、ブックトークなど、絵本をめぐる様々な活動が行われています。ただ一つ問題なのは、かつての文庫運動の悪しき側面と同じものを読み聞かせのボランティアの方が持っていらっしゃるという点です。私は、これを大変危惧しています。文庫運動が出てきたのは40〜50年前、日本がまだ貧しく、本を自由に買うこともできず、学校にもそんなに本がないころのことでした。ある先生が退職され、その退職金で家に絵本を買いそろえて、近所の子どもたちに「おいでおいで、おばちゃんが読んであげる」と呼びかけました。それが文庫運動のスタートです。 しかし、経済が少し上向き始め、一般家庭でも少しずつ本を買うことができるようになると、子どもたちの足が遠のき始めました。そうなると、文庫のおばちゃんとしてはおもしろくありません。自分のところだけが本を独占し、子どもたちに読んであげて楽しい思いをしていたのに、だんだん来なくなってしまう。そうなると困るから、「本は買うものではない。図書館で借りるもの、私のところに来て読むものだ」ということを言うようになりました。これは文庫運動における、ほんのわずかな暗い部分だと思います。大方の部分において、文庫運動が果たした役割は大きいものでした。 しかし、これと同じような現象が読み聞かせのボランティアにも現れてきているのです。ボランティアの方が学校に読み聞かせに行くと、子どもたちは目をきらきらと輝かせて、絵本に注目してくれます。本当に子どもは絵本が好きですから、真剣に聞いてくれます。そうすると、それだけで文庫運動と同じような満足感、達成感を得てしまうのです。そこからスタートして、おのおのの家庭の中でもお父さん、お母さんが絵本を読んであげるというところにまで踏み込めて初めて、本当のボランティアの活動が実ってくるものだと思っているのですが、自己満足だけで終わってしまっているような感じがします。「退職して暇ができた。何かすることはないか。そういえば、学校に本を読みに行く活動がある。あれをひとつやってみよう」。もちろんすべてではありませんが、そういうボランティアの方が増えているのではないかと思います。そういうところが読み聞かせボランティアのちょっとまずいところだと、私は思っています。 |
| きっかけだけではだめ。そこにあるだけでもだめ。 |
 しかし、読み聞かせ活動をきっかけに、「この絵本、楽しいな」「こんな世界もあるんだ」と新しいことを知る驚きが子どもたちの内面を動かし、新たな関心に向かっていくエネルギーになっていることは確かです。そういう意味で、読み聞かせをしてあげるのはとても大事なことなのです。
しかし、読み聞かせ活動をきっかけに、「この絵本、楽しいな」「こんな世界もあるんだ」と新しいことを知る驚きが子どもたちの内面を動かし、新たな関心に向かっていくエネルギーになっていることは確かです。そういう意味で、読み聞かせをしてあげるのはとても大事なことなのです。直木賞作家の志茂田影樹という方がおられます。皆さんご存じですね。あの方も絵本活動をされています。おもしろい頭の格好をして、服にいろいろなものをぶら下げて、派手なパンツをはいて、踊りながら絵本を読むのです。あのパフォーマンスで絵本の読み聞かせをしなければならないとなったら、お母さん、お父さんは大変でしょう(笑)。彼の役割はそうではなく、ああいうパフォーマンスをしながら、子どもたちに「こんなおもしろい本があるぞ。おじさんが読んでいるこの本を一度読んでごらん」と訴えかけているのです。しかし、悲しいかな、多くの子どもはそこで読書がストップしてしまいます。なぜでしょうか。家に大きなテレビはあっても、本はないからです。興味・関心がわいたとき、手に届くところに本がなければ、「おじさんが変な格好をして絵本を読んでいた」という一瞬のおもしろさだけで、きれいさっぱりなくなってしまうのです。 これは、私が商売のために言っているところも実はあります。しかし、ごく普通に考えれば、本に興味がわいたとき、手の届くところに本がなければ、その興味がそこで終わってしまうのは当然です。その世界にさらに深く入っていくことはできません。これは本に限らず、子どもが興味・関心を持つものすべてに言えることです。 子どもたちに「絵本っておもしろい!」ということを伝えるのは、大人の役割です。その大人が本を読まずに、子どもに「本を読め」と言っても、誰も読みません。おやじさんが居間にひっくり返ってビールを飲みながら、子どもに「おい、本を読めよ」と言っても、それはだめです。やはり家にたくさんの本があり、日々、大人が読書をする、あるいは子どもと一緒に読書をするという環境があってこそ、初めて子どもに読書の習慣を身につけさせることができるのではないかと思います。 |
| 人生で3度読むべき絵本 |
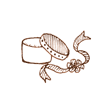 もう一つ皆さんにお話ししたいのは、絵本とは誰のためのものかということです。読書について全く無知な方は、「絵本は幼稚園や小学校1年生、2年生の子どもが読むものでしょう。うちの子は小学校6年生ですよ。何が絵本ですか。もうちょっと高尚な本を読ませなければだめでしょう」とおっしゃいます。しかし、絵本は子どものためだけのものではありません。大人のためのものでもあるのです。
もう一つ皆さんにお話ししたいのは、絵本とは誰のためのものかということです。読書について全く無知な方は、「絵本は幼稚園や小学校1年生、2年生の子どもが読むものでしょう。うちの子は小学校6年生ですよ。何が絵本ですか。もうちょっと高尚な本を読ませなければだめでしょう」とおっしゃいます。しかし、絵本は子どものためだけのものではありません。大人のためのものでもあるのです。そのことを日本全国に改めて知らしめてくれた本があります。河合隼雄、松居直、柳田邦男という、日本の絵本・児童書界を代表する3人の方の講演・討議の内容を収めた『絵本の力』(岩波書店)という本です。その中で柳田邦男は、絵本とは人生で3度読むべきものだと言っています。「まず自分が子どもの時、次に自分が子どもを育てる時、そして自分が人生の後半に入った時。とくに人生の後半、老いを意識したり、病気をしたり、あるいは人生の起伏を振り返ったりするようになると、絵本から思いがけず新しい発見と言うべき深い意味を読み取ることが少なくないと思うのです。生きていくうえで一番大事なものは何かといったことが絵本の中にすでに書かれているんですね」 この本は、絵本が大きく見直される一つのきっかけとなりました。絵本は、子どものためだけにあるのではありません。人生において、少なくとも3回読むものなのです。 また、絵本とは、難しいことが子どものために安易に書かれている本であると思っていらっしゃる方も少なくありません。しかし、断じてそうではありません。例えば、近代の文豪と言われる作家たちでも、本当に純粋な人間は絵本・童話を書きたいと思うのです。代表的なものとしては、芥川龍之介の『杜子春』『蜘蛛の糸』などが挙げられます。また、最近では、野坂昭如が沖縄の戦争の絵本を書きました。本当は、ベストセラー作家と言われているような人たちの中にも、絵本を書きたいと思っている方が大勢いらっしゃいます。でも、書けないのです。なぜでしょうか。絵本の文章や絵は、子どもの純粋な目で人間や世界や自然、つまり森羅万象を見ることができなければ、書くことができないからです。絵本を書くということは、本当に難しいのです。 いろいろな作家が絵本や童話に挑戦してみたいと考えます。有名な作家で、実際に絵本を書いている人もたくさんいます。そして、それが書けるのは、先ほど言ったような純粋な目が持てる人なのです。 |
| “主食の絵本”と“おやつの絵本” |
|
ただ、絵本にもいくつか種類があります。簡単に言えば、“本物の絵本”と“偽物の絵本”です。我々はそれを、“主食の絵本”と“おやつの絵本”と呼んでいます。今、『ももたろう』というタイトルで出ている絵本は、無数にあります。これは永岡書店というところが出している『ももたろう』です。この本は書店で、クルクル回るような棚に置かれています。これは、“くず本”と言っては怒られますが、おやつの絵本です。こちらは福音館書店の『ももたろう』、主食の絵本です。表紙をパッと見ただけでも、その違いは明らかだと思います。 普通の食事でも、毎日、ケーキやあめ玉、アイスクリームなど、おやつのようなものを食べさせてばかりいたら、栄養が偏ってしまいます。やはりしっかりと主食を食べさせなければ、子どもの体はまともに育ちません。体の成長に栄養が必要なように、心の成長にも栄養が必要です。その栄養の一端を絵本が担っているとすれば、どちらの絵本を選べばいいか、自ずと見えてきます。主食の絵本を中心にしていれば、ときどきおやつの絵本を見せても、心の育ちには大きく影響しないでしょう。しかし、先ほどの柳田邦男さんの言葉を借りれば、おやつの絵本は人生で3回も読む必要のないものであり、私は1回も読まなくてもいいと思っています。ところが、安易にこちらを選んでしまう方が多いのです。 |
| 実年齢と読書年齢 |
もう一つ、大きな間違いがあります。それは、絵本の対象年齢についてのことです。「私の子は5年生だから、5年生レベルの本を読ませればいい」と思っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。しかし、小さいころから絵本の読み聞かせや読書習慣に触れていない5年生の子どもが、いきなり5年生レベルの本を読んでも、おもしろくも何ともありません。逆に言えば、小さいころから読み聞かせをしてもらっていた子どもは、自分の年齢よりも上のレベルの本を読むことができます。絵本年齢と実年齢はイコールではないのです。ですから、5歳になっていても、まだ『いない いない ばあ』(松谷みよ子/ぶん、瀬川康男/え、童心社)を読んでいなければ、『いない いない ばあ』からスタートすればいいのです。 こう言うと、多くのお母さん方は「何を言っているの。赤ちゃんの絵本じゃないの」とおっしゃいます。そこに大きな勘違いがあるのです。小さいころから絵本の世界に触れたことのない子どもは、絵や文章を理解する力が育っていません。言葉から、その情景をイメージする能力が育っていないのです。ですから、おもしろくも何ともありません。苦痛なだけです。そこが絵本との出会いの難しいところなのです。絵本を選ぶときには、そういうところに気をつけていただければと思います。
こう言うと、多くのお母さん方は「何を言っているの。赤ちゃんの絵本じゃないの」とおっしゃいます。そこに大きな勘違いがあるのです。小さいころから絵本の世界に触れたことのない子どもは、絵や文章を理解する力が育っていません。言葉から、その情景をイメージする能力が育っていないのです。ですから、おもしろくも何ともありません。苦痛なだけです。そこが絵本との出会いの難しいところなのです。絵本を選ぶときには、そういうところに気をつけていただければと思います。
|
| 知識ではなく、智恵となる絵本 |
|
『わすれられないおくりもの』(スーザン・バーレイ/さく・え、小川仁央/やく、評論社)という有名な絵本があります。森のみんなに慕われていたアナグマが死んでしまい、みんな嘆き悲しむのですが、それぞれが思い出を語っていくうちに、彼が残してくれた多くの大切なものに気づき、いつしか楽しい思い出に変わっていくという物語です。 先ほどご紹介しました『絵本の力』の中で、柳田邦男は、この『わすれられないおくりもの』についてのエピソードを紹介しています。細谷亮太という方をご存じの方も多いと思います。聖路加国際病院の小児科部長をしておられる方なのですが、この方の『いのちを見つめて』(岩波書店)というエッセイ集に収められているエピソードです。細谷先生はある時、脳死状態に陥って、助かる見込みの少ない2歳の男の子の母親から相談を受けたそうです。その子には、5歳のお兄ちゃんと8歳のお姉ちゃんがいたのですが、その子たちが弟の状態、つまり“死”というものがまだ理解できない。どのようにわからせればいいのでしょうかという相談でした。そんなお母さんの気持ちを受けて細谷先生は、その2人の子どもたちに、弟のベッドサイドで『わすれられないおくりもの』を読み聞かせてあげたそうです。すると、子どもたちは目にいっぱいの涙を浮かべて、しっかりとその絵本を見つめていたというのです。そして読み終わった後、「アナグマ君はおじいさんになって死んだけれど、もっと小さいうちに死ぬものもいるんだ」と、子どもたちに弟の“死”について語ってあげると、2人とも大きくうなずいたそうです。 柳田邦男も、57歳のときに次男を亡くされています。それが、その年になって絵本を読むきっかけとなったということです。自分の愛していた肉親の死というものは、大人にだってなかなか受け入れがたいものです。幼い子どもにとっては、なおさらでしょう。そんな非常に難しいことを、1冊の絵本を読むことによって、素直に、そして深く子どもの心に伝えられるのです。非常に強い感慨を持って、柳田邦男はこのエピソードを紹介しています。 絵が描いてあれば絵本だということではありません。いい絵本と、そうでない絵本は区別していただきたいと思います。それから、読んだ後、子どもに「何が書いてあった?」「どうして、ああいうことをしたのかな?」などと聞くような読み聞かせは下の下、読まないほうがましです。もちろん、子どもの自主的な質問には、親として答えてあげたり、一緒に考えてあげたりしなければいけませんが、親から一方的に絵本の内容について質問することはやめていただきたいと思います。 |
| 心ゆさぶる時を一緒にすごして |
 そのようなことをきちんと考えていただいて、まずは自分のお子さんに絵本を読んであげてほしいと思います。きっと子どもたちは、とても喜ぶことでしょう。なぜなら、絵本を読んでいる間、大好きなお父さん、お母さんを完全に独占でき、世界を共有できるのですから。子どもにとって、こんなにうれしいことはありません。そういう親と子のつながりがいくつも積み重なっていくことで、子どもの心は豊かに育っていきます。そうして育った子どもは、お母さんが困るようなこと、お父さんが嘆き悲しむようなことは決してしないでしょう。
そのようなことをきちんと考えていただいて、まずは自分のお子さんに絵本を読んであげてほしいと思います。きっと子どもたちは、とても喜ぶことでしょう。なぜなら、絵本を読んでいる間、大好きなお父さん、お母さんを完全に独占でき、世界を共有できるのですから。子どもにとって、こんなにうれしいことはありません。そういう親と子のつながりがいくつも積み重なっていくことで、子どもの心は豊かに育っていきます。そうして育った子どもは、お母さんが困るようなこと、お父さんが嘆き悲しむようなことは決してしないでしょう。読み聞かせをするということは、何かを教えるのではなく、親子が一緒に過ごす時間をつくるということです。親と子が肌と心を触れ合わせる時間の積み重ねは、きっと家族の関係をより緊密なものにしてくれることでしょう。最近、同じ屋根の下にいながら、親子が遠く離れたところにいるような家庭が増えてきました。そういう家族の関係をベースにして、不幸なことがたくさん生まれています。どうか皆さん、子どもたちにいい絵本を読んであげて、楽しい時間をたくさん過ごしてあげてください。 最初に言いましたように、読書をするということは、心をどんどんはぐくんでいくことです。それはすなわち、子どもたちが“人間”になっていくことです。読書というものは何物にも代え難いものです。100万円のテレビを買うところを50万円のテレビにして、本を買ってください。そして、本を買うときには、ほるぷから買っていただきたいと思います(笑)。 絵本、読書、読み聞かせというものは、今までお話ししてきた以上に、まだまだすごい力を持つものだろうと思います。どうかお子さんと一緒に、楽しい読み聞かせの時間をつくってください。ありがとうございました。 |