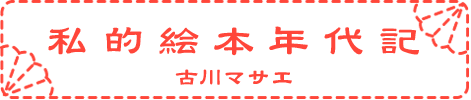 からすたろう −2− ―前号よりつづき― いそべ先生がゆったりと椅子に腰をかけ、机の角をはさんで少年が少しうつむきかげんに立っている場面が出てきます。 ときどき先生は、まわりにだれも いないとき、ちびとふたりだけで はなしをすることが ありました。 この「だれもいないときに」「ふたりだけで」というところが大事なのです。恐らく少年のほうから積極的に話すことはなかったのでしょうが、担任の先生と2人だけで秘密を分け持っているという、ふつふつとした喜びが心の中に広がり、それは少年のひそかな自尊心を育てていくことになります。わたしがこのシーンの絵に強くこだわるもう一つの理由は、いそべ先生と少年の視線が直接交わらないように描かれていることです。たいていの場合、向き合う形になりがちなのですが、いそべ先生は少年と直角に座っています。そうすると、緊張している少年は先生の視線を直接受けないし、先生に気づかれずにこっそりと相手を見ることができます。いそべ先生は無意識にそういう配慮をしたのでしょうし、作者もまた自然に配置したのでしょうが、子どもと話すときの場面構成としては完璧です。 さて、物語はふたりだけのはなしから、最後の学芸会「からすの鳴き声」へ展開していきます。いよいよクライマックスです。 はじめに ちびはかえったばかりの あかちゃんからすを まねました。 つぎに かあさんからすのなきごえを まねました。 (中略) からすがうれしくてたのしいときは、どんなふうになくかも してみせてくれました。 だれのこころも、ちびが まいにちかよってくる とおい山のほうに つれてゆかれました。 いそべ先生は、少年がなぜからすの鳴きまねができるようになったかを説明します。毎日、たった1人で山道を通った少年のことを…。 ぼくたち みんなは そのながいあいだ、ちびに どんなにつらくあたったかを おもいだしてなきました。 こうして少年は、肩を自慢げにはって山の仕事に励みます。 この本には、教職員研修のテキストとして、大いに助けられました。共感的に児童生徒を理解する、あるいは「子どもの自尊心を高めるには」という課題を読み取る作業を通して考えてもらったのです。単純な絵と文をもとにして、教師である自分を振り返る研修は好評でした。 そして今、わたしは6歳の孫娘とFAXのやりとりをしながら、2人で絵本作りの真似事をして楽しんでいます。子ども時代からわたしに様々な影響を与えてくれた絵本と、これからもずっとともに。 |
第3回へ★
