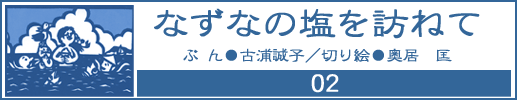 |
|
むか〜し、昔のお話です。 あるところに、貧しいけれど正直で心やさしい若者がおりましたとさ。 神様がごほうびに、何でも望んだものが出る、不思議な石臼をくださいました。 若者は、困っている人たちのために食べ物や着物を出してあげました。 それを見ていた、欲張りで意地悪な兄さん。石臼を盗み出し、遠い国へ行って大金持ちになろうと、船で海へこぎ出しました。 船の上でおまんじゅうを食べ過ぎて、塩辛いものが欲しくなった兄さんは、石臼に命じました。「塩よ出ろ!」 石臼からはどんどん塩が出てきますが、止め方を知りません。石臼もろとも船は沈んでしまいましたとさ。 今でも海の底で石臼は回り続けているので、海の水はしょっぱいのです。 そのほかにも「塩」が登場する物語はたくさんあります。グリム童話の「泉のそばのガチョウ番の女」もその一つ。「お父様を塩のように愛しています」という末娘の言葉に腹を立てた王様。その娘を森へ追い払いますが、後に塩の大切さ、娘の愛の深さを知って、娘を捜し出し、幸福に暮らしましたとさ……。 では、本当のところはどうなのでしょう。海が塩辛いのは、実は植物のおかげ。前回お話ししたように、植物とそれを分解する菌がつくった土のエキスが流れ込んだ海の中で、また生命が生まれ、死に、分解され……。そんなすべての生命のエキスが、海の塩のもとなのです。 私たちになじみ深い海塩は、海水の水分を乾燥させてつくりますが、湿度が高く、冬場の日照時間が短い日本の気候に適しているとは言えません。四方を海に囲まれていながら、昔から塩づくりには大変な苦労があったのです。 海藻に海水をかけ、乾かして凝縮させたり、その海藻を燃やした灰を使う藻塩法、砂に海水をまいて乾燥させる揚げ浜式、潮の干満の水位差を利用する入り浜式、竹の枝や稲穂に海水をかけて乾かす流下式、そしてイオン交換膜法へと移ってきたのです。  那波おじさんが案内してくれたのは、高さ6メートルの流下式循環タワーのてっぺん。不安定なはしごを登ると、間越(はざこ)の美しい海が視界いっぱいに広がります。背後には豊かな原生林。南から上ってくる、温かで栄養分たっぷりの黒潮が半島にぶつかって二つに分かれ、湾に流れ込んでいます。
那波おじさんが案内してくれたのは、高さ6メートルの流下式循環タワーのてっぺん。不安定なはしごを登ると、間越(はざこ)の美しい海が視界いっぱいに広がります。背後には豊かな原生林。南から上ってくる、温かで栄養分たっぷりの黒潮が半島にぶつかって二つに分かれ、湾に流れ込んでいます。満潮の1時間ほど前、海の水が最もきれいなときにこのタワーに取り込みます。最上段のパイプから噴水のように吹き出した海水は、ジグザグに張られたネットに流れていきます。下にたまった海水をくみ上げては流す作業を繰り返すうちに、お日様や風の力で水分が蒸発します。ここで海水を塩分濃度12%以上にまで濃くします。 冬の乾燥した時期には作業は順調に進みますが、雨が多く湿度が高いときにも変わらずよい塩をつくるために、濃くなった海水は隣の貯蔵樽にためておきます。その大きな杉樽は、大分県内のしょうゆ蔵から譲り受けたもの。80年以上も前につくられた、大人の背丈以上もある樽は、壊され、燃やされてしまう運命だったのですが、ここで新しい役目を果たしています。 そのまた隣、木の骨組みにビニールが張られた三角形の建物が「天日ハウス」。お日様パワーを十分に受けられるように、ヒノキの四角い皿が3段の棚に置かれています。その皿の上でさらに水分を蒸発させていくと、2〜4カ月で自然の天日塩ができ上がります。 おじさんたちの仕事は、「ころ合いを見計らうこと」。うっかりしていると、海水の中の石こう分が固まって、トゲトゲの結晶だらけに……。「ほったらかしたら、塩が怒るとたい」と那波おじさん。 最後にのぞいたのが、塩場の端で煙を上げる「釜屋」です。大きな(まるで魔法使いのおばあさんがかき混ぜているような)鉄釜では、タワーで濃くなった海水を2日から3日かけてじっくりと炊き上げます。炊き上げが近づくと、釜につきっきり。大きな木じゃくしで天地返し(底と上をひっくり返して混ぜる)をしながら、火を落とすときを見極めます。 「目、鼻、耳、舌(ベロメーター?)が頼り。あとは、ゆっくり休んでうまい塩になってくださいって祈るだけやね」 木の樽に移して、にがりと一緒に熟成させれば、まろやかな釜炊塩のでき上がり、でき上がり。 こうしてできた天日塩と釜炊塩は、手作業でゴミなどを取り除き、袋詰めされます。時間をかけ、人の手で丁寧につくられた塩は、結晶が大きくしっとりとしています。口に含むと、塩なのに柔らかな甘みを感じます。これって、お日様と風と温かな海の味……? 次回は、なずなの塩を「こん塩は生きちょる」と言ったお百姓さん(尊敬語です)、赤峰おじさんに会いに行きましょう。 |
「絵本フォーラム」40号・2005.05.10
前へ★次へ
