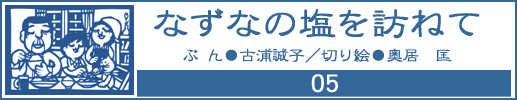 |
|
動物は塩なしでは生きられません。自然の輪の中では、塩が足りなくなるのは生命にかかわること。肉食の動物はえさの動物の体から塩分をとることができますが、草食の動物は、テリトリーの中にそれぞれの塩場を持っているそうです。 牛も塩が大好き。平安時代の女性たちが好きな殿方の牛車を止めようと館の戸口に塩を盛ったのが、料理屋さんなどのお店の入り口にある盛り塩の始まりとも言われます。 赤峰おじさんの農園でも、飼っていたブタが次々に死んでしまったことがあったそう。「塩切れじゃ。人間も塩が足らんと元気がなくなる。力が出んし、病気も引き起こすよ」とおじさん。 昔の人は、体力や精神力にも影響する塩の力をちゃんと知っていたよう。塩をしっかり食べた兵隊は強くなって、戦に勝ちます。戦争が終わって塩を減らせば、兵隊はおとなしくなって、平和になる……。ですから、自分の権力を広げ、手に入れた土地を治めようとする王様たちは、競って塩の産地を支配しようとしたのだそうです。 私たちの国では、願い事をかなえるために好きなものや大切なものを断つ(我慢する)という風習がありました。「茶断ち」や「酒断ち」などの中でも、一番大変なのが「塩断ち」。野口英世のお母さんも、息子のために「塩断ち」をしていますと手紙に書いています。自分の生命をかけても大切な人のために祈ったのでしょうね。 それなのに、いつの間にか「塩分をとりすぎると血圧が上がる」「健康のために塩分はとりすぎないように」と言われ、減塩食品が大はやり。どうにも不思議な話……? この減塩信仰は一体どこから来たのでしょう。 戦後間もなく、アメリカの博士が日本人に高血圧が多いことに注目して調査したところ、東北のある地方では高血圧と脳卒中が多く、塩分の多い食事をしていることから、塩がそれらの病気の原因ではないかと仮説を立てました。その後、塩をたくさん食べても高血圧が少ない地域もあることがわかり、この仮説は取り下げられたのですが、一度興った減塩信仰は収まりませんでした。 また、別のアメリカの学者によるネズミの実験もきっかけのようです。10匹のネズミに、通常の20倍の塩を6カ月与え続けたら、10匹のうち4匹が高血圧になったというのです。でも、そんなに多量の塩を6カ月もとり続けることができるのか、それだけの塩を与え続けても残りの6匹が高血圧にならなかったのはどうしてなのか……。さまざまな疑問を残しながら、肉食の欧米での減塩の考え方が、こうした仮説や実験のもとに信じられてしまったようです。  今では、高血圧や脳卒中は、遺伝やストレス、肥満、運動不足、タバコやアルコールなどのさまざまな原因が組み合わさって起こるということがわかりました。もちろん、「過ぎたるは及ばざるがごとし」ですから、砂糖や油脂と同じように、塩のとりすぎに気をつけることも体にとって大切でしょう。
今では、高血圧や脳卒中は、遺伝やストレス、肥満、運動不足、タバコやアルコールなどのさまざまな原因が組み合わさって起こるということがわかりました。もちろん、「過ぎたるは及ばざるがごとし」ですから、砂糖や油脂と同じように、塩のとりすぎに気をつけることも体にとって大切でしょう。動物は本来、自分の体に必要なものを必要な量しか食べません。どんなにごちそうを並べても、おなかいっぱいなら知らん顔。ライオンだって、自分と家族が食べる分だけしか狩りをしません。 私たち人間はどうでしょう? 目の前においしそうなものがあると、満腹でも欲張ってもう一口パクリ。好き嫌いを言って同じようなメニューに偏ったり、添加物と濃い味つけに慣れてしまったり……。人間と生活するペットまで、肥満や生活習慣病に悩んでいます。 自然の輪っかは、その土地や季節に合った食べ物をちゃんと準備してくれますから、その中から体が欲しがるものを腹八分で食べればいい。例えば、キュウリやトマトといった夏野菜は体の熱を取ってくれますし、カブやゴボウ、大根などの冬の根野菜は体を温めます。また、風邪のひき始めにはショウガ湯、せきやのどの痛みにはキンカンや黒豆、大根の絞り汁が効くなど、土から生まれる作物には、いろいろなパワーがあるのです。 昔から伝えられる食べ合わせにも、意味があります。例えばウナギと梅干しは脂と強い酸の食べ合わせ、天ぷらとスイカは脂と水分の組み合わせで、消化不良を起こしやすい……。長い間の経験から学び伝えられてきた大切な知恵を忘れてしまっていることこそ、本当に恐ろしいことなのかもしれません。 外国から輸入される食品、添加物だらけの加工食品、ハウスで1年中同じようにつくられ、季節を忘れた作物……。それらに惑わされ、本当に体が必要としているもの、必要な量を選び取る力を私たちは失っていないでしょうか。 「塩づくりにかかわってみて、自然からたくさん教えられたよ。すべての命は使命を持って楽しんで生きている。人間だけが眉間にしわを寄せて生きる。人も自然の大きな輪の中で楽しんで生きていければいいね」となずなのおじさんたち。野菜から始まって塩づくりへ……。なずなの塩の夢はどこまで広がっていくのかな。 |
「絵本フォーラム」43号・2005.11.10
前へ
