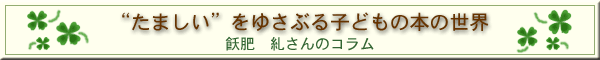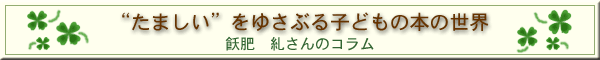「絵本フォーラム」第14号・2001.1
●●3
幼な子とコミュニケーションできますか。
いないいないばぁ遊び
 また、だ。哀しく悲惨なニュースがつづく。朝刊に目を遣ると「3歳の娘段ボールに閉じこめ餓死−容疑の21歳夫婦逮捕」(『朝日新聞12月12日号』)の見出しが目をうばう。3歳児の平均体重は12〜15キロとされるが、この幼女はなんと5キロしかなかった。通常の子どもの3分の1である。母性や父性を顕在化されることのできない若い両親、幼い自らの子どもとコミュニケーションできない親たちがどんどん出現している。
また、だ。哀しく悲惨なニュースがつづく。朝刊に目を遣ると「3歳の娘段ボールに閉じこめ餓死−容疑の21歳夫婦逮捕」(『朝日新聞12月12日号』)の見出しが目をうばう。3歳児の平均体重は12〜15キロとされるが、この幼女はなんと5キロしかなかった。通常の子どもの3分の1である。母性や父性を顕在化されることのできない若い両親、幼い自らの子どもとコミュニケーションできない親たちがどんどん出現している。
わたしには、0歳7ヶ月の孫がいる。孫の体重は10キロ。ようやくハイハイをはじめ、何事か声を発しながら手当たりしだいにモノをいじくりまわす。この愛すべき宇宙人と付き合うのは無条件に楽しく、愉快だ。この“無条件に”“楽しく、愉快”という心の動きや、輝く新しい生命と心を通わせる喜びはたとえようのないものである。
母親であるわが娘は、当然のように、たえず何事かの言葉を語りかけている。シャワーのように語りかける母の言葉に3ヶ月、5ヶ月と月日を数えるごとに幼な子の反応は豊かになり、喜怒哀楽の表情を見事に示してくれるようになった。
子守歌を歌わなくなった母親が多くなった。授乳やおむつの交換なども黙ってやる親が増えているのだという。“無条件に、楽しく、愉快な”幼な子との付き合いに言葉なしではもったいないではないか。しかも、幼な子といっても、立派なひとりの人間なのだ。母親があふれるように言葉を語り浴びせる。それが幼な子の“たましい”をゆさぶり、親と子の確かな愛情関係を成立させていくのである。
「お母さんが、ほらほら、いないいない−いない、いない」、「バァー!」。かつて、幼な子のいる家庭ではどこでも、いつでも見られたシーンである。語り手の両親や祖父母、あるいは兄姉が、顔を両手でかくして「いないいない−」とやり、いっきに両手を解いて表情ゆたかに目をみはり、「ばぁっ」「バァーッ」とやる。6ヶ月をすぎるころから幼な子は見事に反応する。腹を抱え全身を震わせて「キャッキャッ」「クックゥッ」、「キャッキャッ」と大喜びなのである。1歳にもなると子ども自身が大人を相手にかわいい小さな両手を顔に当てて「いないいない、ばぁっ」とやってみせてくれる遊びだ。
この遊びが絵本になった。にゃあにゃ、くまちゃん、ネズミにこんこんぎつね、そして男の子ののんちゃんが登場して−。『いない いない ばあ』(松谷みよ子・文/瀬川康男・絵)の誕生である。1967年春の刊行であった。
まだまだ、どこの家庭でも“いないいないばぁ・遊び”を普通に見ることのできた時代。この絵本の刊行には否定的な批評も多かった。曰く「いないいないばぁ・遊びは行う〈やる、する〉あそびで、本で見るもんじゃないだろう」というのである。ところが、『いない いない ばあ』は多くの読者に喝采を受けるように歓迎された。1967年という時代。高度成長のただなかにあり、核家族やら共働きが時の潮流とされだしたころで「いないいないばあ遊び」と縁遠い若い夫婦や家庭が増え始めていたのであった。
また、母と子の実際を愛情ゆたかに観察し、むだのない、たしかなことばで書き綴った松谷と、シンプルなフォルムに暖かい色彩で優しく描いた瀬川のコンビネーションがこの絵本に動きを与え、音や声まで伝えてくれるのだ。すでに103刷を数えるというからこの絵本で育った子どもたちはどれくらいの数にのぼるのだろうか。 |