第11期「絵本講師・養成講座」(芦屋会場)第5編は2014年10月25日(土)、ラポルテホールで開催されました。秋晴れの爽やかな青空に思わず深呼吸したくなるような日です。
午前中は90歳で亡くなられた中川正文先生(作家・元大阪国際児童文学館特別顧問・「絵本で子育て」センター顧問)のDVD講座「絵本・わたしの旅立ち」で始まりました。
中川先生のお声は、闘病中の為、小さな声の部分もありましたが、ユーモアを含んだ表現に会場では笑い声も聞かれました。
10代のころから創作を始められ児童文学者協会の創立会員でもあった先生は、簡単に答えを求めすぎる大人に対して、まずは自分で調べることの大切さを話されました。また、絵本は子どもに「与える」「下ろす」ものではない。親と子が、教員と子どもが、一冊の絵本を通して経験を分かち合い、共に成長するというのが子どもと大人と絵本の基本的な関係であると強調されました。
テレビは一方的に送られてくるのを受動的に受け取る。一度きりのものであるのに対して、本は自分の方からも付き合いが選択でき、何度も読み直すことが可能です。
母親は一回読んで子どもが受け入れられなかったと、早合点して読むことをやめるのではなく、繰り返し読んでいくうちに、絵本の奥深さに到達する。だからこそ「少々の失敗であきらめない」という先生の言葉にたくさんの方が勇気付けられたのではないでしょうか。
絵本が子どもたちにとってどのような内容であるとよいのかということについてでは、
困難を乗り越えてゆき、社会的に自分の存在を認め、知的要求を満たす絵本であると説明され、家庭に、いつでも必要な時に読むことのできる自分の本を持つことの大切さを語られました。
最後に先生が『すみれ島』(今西祐行/文、松永禎郎/絵、偕成社)を読んでくださいました。先生の声は穏やかでありながらも、力強く心に響きました。特攻隊と子どもたちの関わりの中で、今の平和な世の中はどのような時代を経て得たのか、命の重さを再認識された方もおられるのではないでしょうか。そっと、涙を拭う受講生の姿も見られました。
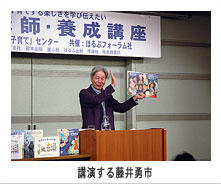 午後の講演は、藤井勇市先生(「絵本講師・養成講座」専任講師)です。「中川正文先生の思い出」「子ども(たち)に絵本を届ける大人の基本的な考え方」についてお話されました。「中川正文先生の思い出」については、10月に藤井先生が出版された、『子どもに絵本を届ける大人の心構え』(「絵本で子育て」センター)でも紹介されています。 午後の講演は、藤井勇市先生(「絵本講師・養成講座」専任講師)です。「中川正文先生の思い出」「子ども(たち)に絵本を届ける大人の基本的な考え方」についてお話されました。「中川正文先生の思い出」については、10月に藤井先生が出版された、『子どもに絵本を届ける大人の心構え』(「絵本で子育て」センター)でも紹介されています。
また、現在の日本には特定秘密保護法をはじめ、集団的自衛権、原発再稼動、沖縄基地問題、消費税増税、TPP、朝日新聞「誤報・謝罪」問題、道徳の特別教科化など、多くの難問が山積されています。
私たちが生きている社会で、何を考えどのように生きてきたのか、未来を託す子どもたちに問われる時が必ず来ます。その時にあなた方はどう答えますか? 藤井先生の鋭い問いかけに皆さん、真剣な眼差しで聞かれています。先生が20歳の時に政治に関心を持ち始めてから今までに見たことのない世の中に進んでいるようで、背筋がざわつくと言われ、私たちは子どもたちに、どのように絵本を届けていくのか、改めて考える事が求められています。
中川先生との思い出では、「絵本講師・養成講座」を始める時に大阪国際児童文学館を訪ねられ、「現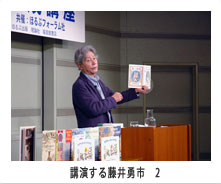 在の家庭に言葉がなくなった。人と人とのリアルな関係がなくなった。家庭の中で本を読むことで会話が増えてくる」のではと話された事、最初は50名の募集から始まり、今では1200名ほどの修了生になっている事など、深くて温かい思い出に会場には笑顔がこぼれました。 在の家庭に言葉がなくなった。人と人とのリアルな関係がなくなった。家庭の中で本を読むことで会話が増えてくる」のではと話された事、最初は50名の募集から始まり、今では1200名ほどの修了生になっている事など、深くて温かい思い出に会場には笑顔がこぼれました。
「三つの『ない社会』で生きる子ども」については、大人である私たちの問題であり、
改善していくには、大人一人、一人が考え、実行してゆくことが求められます。先生が挙げられる「子どもに絵本を届ける大人の基本的な考え」を絵本講師としてしっかりと自分に問いかけ、考えてゆきたいと思います。
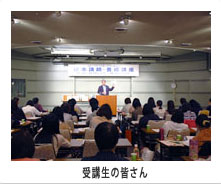 グループワークは今回で5回目になります。どのグループも落ち着いた様子で、修了リポート、今後の活動について、絵本を通して感じたことなどを、それぞれのグループでの課題として、中身の濃い話し合いが進められていました。 グループワークは今回で5回目になります。どのグループも落ち着いた様子で、修了リポート、今後の活動について、絵本を通して感じたことなどを、それぞれのグループでの課題として、中身の濃い話し合いが進められていました。
これから冬に向かってゆきますが、次回はいよいよ閉講式となります。
受講生の皆様の元気なお顔が全員揃うことを願っております。
(とみた・ひろこ) |