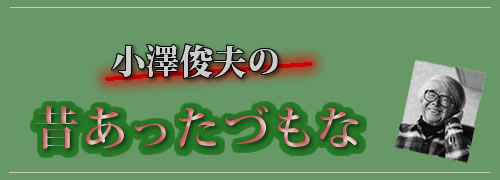犯罪は2度と起こさないという決意
グリム童話研修旅行と北ドイツの旅に行ってきた。グリム研修旅行の最後に、ぼくは、ワイマール憲法で知られるワイマールに一行を案内することにしている。日本の平和憲法の模範となった民主憲法を生んだワイマール共和国時代(1919―1933)の首都だからである。だがそのワイマール共和国は、わずか14年でヒットラーによって打倒され、あの悲惨なナチス時代に雪崩れ込んでいくのである。それを思うと心のふさがる町である。
だが、ワイマールの町に入る手前で、ぼくは一行を「ブーヘンヴァルト強制収容所跡」へ案内する。このことは前にも書いたのだが、今年も実行したのでふれておきたい。
ブーヘンヴァルト(ブナの森)に入ると高い「警告の塔」が左手にそびえている。これには「1945」とローマ数字で書かれているから、共産主義政党が建てたものに違いない。ドイツは1990年に再統合し、共産主義政党は消滅したのだが、現在のドイツ政府もこの「警告の塔」はそのまま保持している。
この塔を過ぎると、右手に当時のいわゆる「囚人」たちを乗せてきた貨物列車の終着駅跡がある。行き止まりのプラットフォームと線路の一部が残されているのである。痛ましい生命の終着駅。
収容所の入口の上の大きな時計は午後3時15分で止まっている。1945年にソ連軍がここに到達した時刻なのだそうだ。鉄格子の門には、「それぞれの者に、ふさわしいものを」という言葉が残っている。「汚れた血のユダヤ人どもには、それにふさわしい仕打ちを与えるのだ」という意味である。ユダヤ人を絶滅しようと考えた狂気の言葉である。
中に入ると、広大な敷地には何もない。バラックの収容棟が立ち並んでいたそうだが、占領したソ連軍が、伝染病を防ぐために直ちに焼き払ったとのこと。今は、見渡す限り何もない墓地なのである。右の隅に死体を焼いたという煙突が残っているだけ。あちこちのバラックの跡に低く横たえられた石碑がある。ポーランド人犠牲者の碑、ユダヤ人犠牲者の碑、ジプシーと言って差別されたロマ人、シンティ人たちの碑などである。その間を歩いていくと、苦しんで死んでいった人たちの霊がそこらじゅうにいるような気配を感じる。
ぼくら一行は小1時間、収容所跡を見てバスに乗った。すると20分ほどでワイマールの町に入る。ぼくはいつも、ほんとに考え込んでしまう。
ゲーテが「ファウスト」をはじめ人類の財産となった作品を書き、シラーがあの「歓喜に寄す」という詩を書き、ベートーヴェンがそれによってあの人類普遍の 「第九交響曲」を書いたのは、わずか100年ほど前のことではないか。しかも、ゲーテとシラーが住んでいたワイマールとこの強制収容所は10キロと離れていない。この時代の近さと距離の近さ、そして180度の逆方向。
国家は短時間にこれほどまでに変容するものなのか。そう考えると、日本も、平和憲法 を持っているからと言って安閑としてはいられない、と改めて思ったことである。強い、強い意志と積極的な行動で平和を守らなければならないと。国の平和は 内部から崩されていく。日本の現状を見ると、そのことを強く思う。
旅の第二週目の最後にベルリンに滞在した。アメリカ空軍の爆撃で破壊されたカイザー・ヴィルヘルム教会の廃墟はまだそのままそびえていた。部分的崩壊があるとかで、修復工事が行われていた。
ベルリン市のど真ん中の広場に、「ユダヤ人のホロコースト警告記念石碑群」ともいうべき広大な石碑群がある。200m四方くらいの広場に、大小の黒い石棺のような石が数百個並べてある。650万人ともいわれるユダヤ人犠牲者を弔う警告記念碑群なのである。近頃はいたずら書きをする者がいるので、監視員が常に回っているということだった。
これはナチスドイツが行った人類に対する犯罪への反省として、平和になったドイツ政府が作ったものである。ああいう犯罪は二度と起こさないという決意を世界にはっきり示している。しかも、首都ベルリンのど真ん中の広場に、数百の黒い石棺を並べて、である。
ドイツと日本に違いはどこから
ぼくはここでもまた日本のことを考えてしまった。従軍慰安婦という言葉で言われている女性に対する犯罪のことは、世界に知られているのに、日本では、まるでなかったかのように言う人間がいる。南京での大虐殺も世界に知られているのに、あれはなかったのだとか、そんな大虐殺ではなかったのだという人間が、だんだん幅を利かせてきている。
日独のこの違いはどこから来るのか。これはきっと文化人類学的な研究に値する大きな問題なのだろうが、ぼくが直感的に感じるのは、過去の過ちをはっきり反省しようという精神の強靭さと、過去は早く水に流して、忘れてすっきりしようという精神の弱さの違いなのではないか、ということだ。強さ、弱さというレベルを外して言えば、自分の結果をはっきり処理するという論理性と、すべては水の流れのようなものよ、として過去を忘れていく曖昧性の違いと言えるかもしれない。
だがそれは世界では通用しないと思う。現在起きている日本と中国・韓国とのいさかいはいつまでも続くことになってしまうだろう。世界という社会の一員としての日本にとって、それは決していいことではないと思う。世界の国々からの信頼はとても得られないと思うのである。
(おざわ・としお)
小澤俊夫プロフィール
1930年中国長春生まれ。口承文芸学者。日本女子大学教授、筑波大学副学長、白百合女子大学教授を歴任。筑波大学名誉教授。現在、小澤昔ばなし研究所所長。「昔ばなし大学」主宰。国際口承文芸学会副会長、日本口承文芸学会会長も務めた。2007年にドイツ、ヴァルター・カーン財団のヨーロッパメルヒェン賞を受賞。小澤健二(オザケン)は息子。代表的な著作として「昔話の語法」(福音館書店)、「昔話からのメッセージ ろばの子」(小澤昔ばなし研究所)など多数。