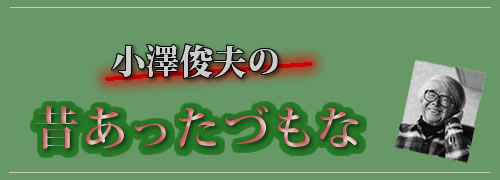犯した罪、苦しんだ過去を忘却の彼方に捨て去らない
ベルリンの有名なブランデンブルク門からほど遠からぬところに、東西分割の時代にチェックポイント・チャーリーという検問所があった。当時ベルリンは4地域に分割されて統治されていた。アメリカ、イギリス、フランス、東ドイツ政府である。それぞれの区域が検問所を設けて、通行を厳しく監視していた。 1961年に東ドイツ政府がその統治区域の境界線に厳重な壁を建設してからは、西ベルリン全体が籠の中に閉じ込められることになった。アメリカ統治区域との間の検問所はチェックポイント・チャーリーと呼ばれていた。その検問所の詰所が現在でも保存されており、その脇に「チェックポイント・チャーリーハウス」という記念館がある。
久しぶりに行ってみると、そこは大変な賑わいだった。チェックポイントだから、そもそも狭い道である。そこに、肩がぶつかるほどの観光客が集まっていた。聞こえる言葉は様々なので、世界から広く集まってきているのだろう。若者がほとんどだった。
記念館に入るにも、長蛇の列だった。中は詳しい、生々しい展示だった。壁の建設が開始されたころ、建物の2階、3階から西側の道路に飛び降りる人々、それを助ける人々の写真。鉄条網の東と西に分かれてしまった夫婦の夫のほうが、幼い子を妻に渡す写真。西に脱出するための地下道を掘る人々の写真。土を排出する小さいトロッコの実物。狭い地下道を腹這いになってくる人々の写真。チェックポイントを強行突破しようとした小型自動車の実物。フロントガラスの内側に弾丸除けの鉄板が張ってある。運転者が前を見られるように小さな穴がたくさん開けてある。だが、その脇に、弾丸が貫通した穴が数個あった。運転者は多分射殺されたのだろう。胸の痛む展示が上階まで続く。
1966年、ぼくは初めてドイツに行った。年の暮れに西ベルリンについて、ドイツ人の友人宅に泊めてもらったのだが、「一昨日、チェックポイント・チャーリー近くの壁で一人射殺されたのだ」と聞かされた。東ベルリンの男性が、壁を乗り越えようとしたとき東側からの射撃が命中して、東側に落ちてしまった。男のうめき声が聞こえ、壁の西側では救急車などが待機したがどうすることもできなかった。そのうちにうめき声は消えていった。東側は男をさらし者にして殺したのだ、ということだった。
チェックポイント・チャーリーハウスにも写真が展示されていたが、ベルリンの壁の建設は1961年のある日、突然始まった。最初はレンガを積み上げてコンクリートで固めていく単純な工事だったそうだ。だが終いには西ベルリンを周りから完全に遮断する強固な壁になっていった。東ベルリンからの脱出者が後を絶たないので、東ドイツ政府は壁の内側に鉄条網を幾重にも張り巡らし、地雷原も作ったということだ。壁とはいうものの、実際は幅150mにも及ぶ分離地帯だったということだ。
1989年に壁が解放され、1990年に東西ドイツの再統合が実現した後、壁はほとんど取り除かれたが、今回訪問して確認できたのは、ブランデンブルク門近くに、壁が約200mにわたって保存されていることであった。ここにも多数の若い観光客が詰めかけていた。
そして驚いたことに、壁が立っていた跡が、2列に並べた石の線で、ベルリン市内の道路に延々と明示されていた。壁そのものを一部保存するだけでなく、ベルリン市内中の道路に、広場に、壁が立っていた線を明示する。過去を保存しようという、ドイツ人の強い意志を感じた。
ベルリンの壁は共産主義政権である東ドイツ政府が建設したものである。西ドイツ国民だったドイツ人に責任があるわけではない。東ドイツ国民であったドイツ人にとっては被害の歴史である。だが東ドイツ政府もドイツ人の政府であった。ナチスドイツの場合にも、非人道的な政策を実行したのはナチス政権だが、ドイツ国民は1932年の選挙で、ナチス党を第一党にし、翌年には政権をゆだねてしまったのである。その意味でナチス政権の成立にはドイツ人全体に責任がある。
1990年の再統合以来、ドイツ政府が自らの過去について取っている政策は、ドイツ人が人類に対して犯した罪を世界に対してはっきり認め、ドイツ人が苦しんだ過去もはっきり認め、それを忘却の彼方に捨て去らないように、証拠を残しておくことであると思う。もちろん国内にはいろいろな意見がある。ぼくも批判的な意見を直接聞いたことが何度もある。「われわれはいつまで謝らなければならないのか」と。しかし、国全体としてはこの政策はしっかり支持されて、続いているのである。
政府の意向を汲んで市民を抑圧 一番恐ろしいこと
自らが犯した人類への罪の証拠をはっきり残しているドイツに感銘を受けて帰国したら、なんと、新聞では戦争の跡を消そうとする動きが各地で起きていることが報じられていた。日本国内で、戦争遺跡と言えるものは3万か所あると言われているが、国や地方自治体によって保護されているのはそのうち216件に過ぎないとのこと。しかも近頃では、戦争の加害記述を自粛する動きが強まっているという。
群馬県は、県立公園に建てられた朝鮮人強制連行犠牲者追悼碑の撤去を、管理する市民団体に求めたという。大沢正明知事は、「存在自体が論争の対象となり、憩いの場である公園にふさわしくなくなった」と述べているという。長崎市でも在日本大韓民国民団長崎県地方本部が平和公園内に計画した韓国人原爆犠牲者慰霊碑の建設が保留になっている。「強制労働と虐待」などの文言に「平和公園が政治目的に利用される」などの抗議が市に対して相次いだためという。埼玉県東松山市の平和資料館では、展示されている年表から「慰安婦」「南京」の文字を削除した。大阪市と大阪府が共同出資する大阪国際平和センターも、加害の歴史を大幅に縮小する計画という。
記念碑だけではない。さいたま市大宮区の三橋公民館では、市民の詠んだ俳句を月報に掲載することを拒否したということである。その句とは「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」というのである。そもそも公民館は住民の学習の自由を保障する責務があるのだから、この俳句の掲載拒否は社会教育法違反である。こんなことがまかり通るようでは、公民館で九条の問題や戦争の問題は話せなくなってしまう。公民館の職員という公務員が、今の政府の右傾傾向に迎合して、勝手に拒否したのだろう。末端の公務員が時の政府の意向を酌んで市民を抑圧するという構図は、戦争中とまったく同じである。この雰囲気 が世の中の空気を決めてしまう。これが一番恐ろしいことなのである。
自らが起こしたあの戦争に対する責任の取り方の、日独のこの違いはどこから来るのだろうか。責任を取らず、水に流すようになんとなく消していく。内向きに、日本国内だけのことならそれでうやむやにできるかもしれないが、世界の国々との付き合いでは通用しない。
世界の中に日本という国を置いて考えたとき、これは全く惜しいことである。日本は、戦後の約70年間、平和憲法のもとで戦争をしないできた。アジアの国々に、襲ってこない安心な国という信頼感を与えてきた。そして、文化的には世界に通用する人材を生み出してきた。情報科学、医学などの分野でも世界に貢献してきた。それだからこそ、アジアの国々、中近東の国々といい関係を結んでこられたのである。特に中近東のイスラム諸国と。
だが、あの戦争への反省を日本人はしていないのではないか、という疑いが生まれつつあるのが、現在の状態である。安倍首相はそのことには目をつむって、ひたすら軍事大国への道を突き進もうとしている。われわれ日本人がなんとしてもブレーキをかけなければ、引き返すことのできない状態になってしまう。
(おざわ・としお)
小澤俊夫プロフィール
1930年中国長春生まれ。口承文芸学者。日本女子大学教授、筑波大学副学長、白百合女子大学教授を歴任。筑波大学名誉教授。現在、小澤昔ばなし研究所所長。「昔ばなし大学」主宰。国際口承文芸学会副会長、日本口承文芸学会会長も務めた。2007年にドイツ、ヴァルター・カーン財団のヨーロッパメルヒェン賞を受賞。小澤健二(オザケン)は息子。代表的な著作として「昔話の語法」(福音館書店)、「昔話からのメッセージ ろばの子」(小澤昔ばなし研究所)など多数。